2021年と2022年の道路交通法改正により、これまで対象外だった白ナンバーの社用車にもアルコールチェックが義務付けられました。
本記事では、アルコールチェック義務化の背景や対象となる事業所の条件、具体的な実施方法、違反した場合の罰則について詳しく解説します。
安全運転管理者はもちろん、企業のコンプライアンス担当者も、円滑な運用体制を構築するために必要な情報を網羅的に確認できます。
目次 / このページでわかること
営業車のアルコールチェック義務化とは?道路交通法の改正内容を解説
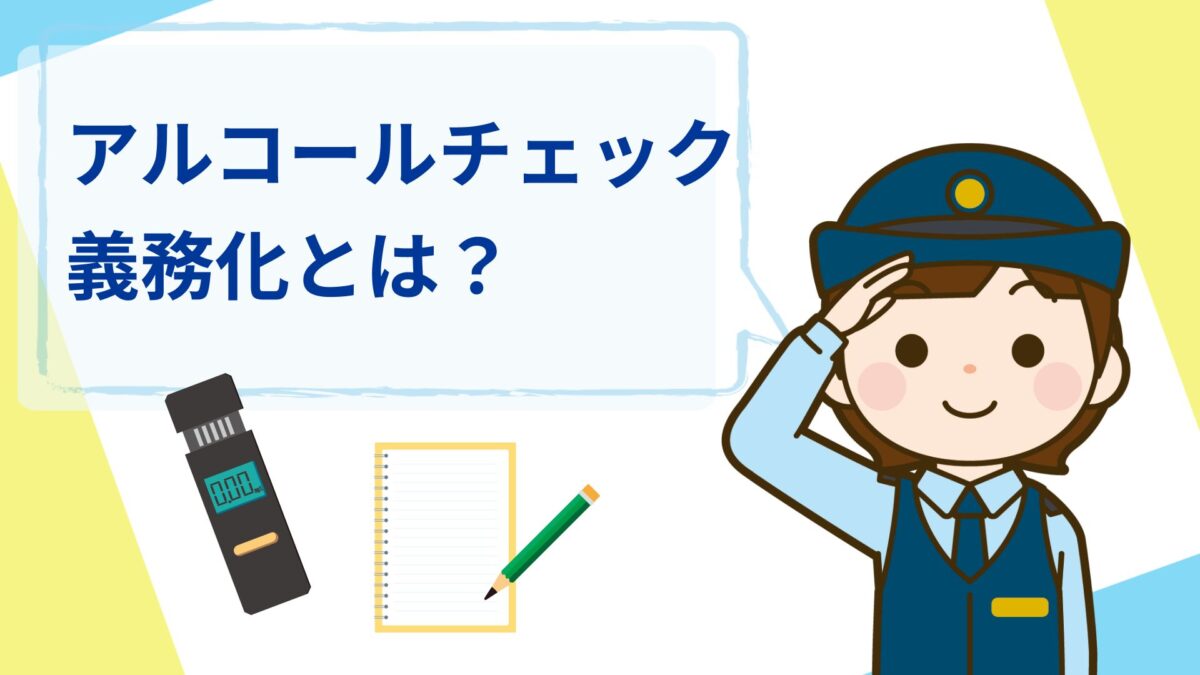
このアルコールチェック義務化は、飲酒運転による悲惨な事故を防ぐことを目的としています。
ここでは、法改正の具体的な内容と、段階的に施行された義務化のスケジュールについて詳しく見ていきます。
飲酒運転事故を背景に白ナンバーの社用車も対象へ
2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバーのトラックによる飲酒運転死亡事故が、法改正の直接的なきっかけとなりました。
この事故を受け、これまで緑ナンバーにのみ課せられていたアルコールチェックの義務が、白ナンバーの社用車を一定台数以上使用する事業者にも拡大されることになりました。
飲酒運転の根絶は社会全体の課題であり、企業もその社会的責任を果たすことが求められます。
この義務化は、事業活動における車両利用においても、安全管理体制の強化を促すものです。
運転者の安全意識向上だけでなく、企業としてのコンプライアンス遵守の観点からも、この規定を正しく理解し、適切に運用することが不可欠です。
2段階で施行されたアルコールチェック義務化のスケジュール
アルコールチェック義務化は2段階のスケジュールで施行されました。
まず2022年4月1日から安全運転管理者が運転者の運転前後に酒気帯びの有無を「目視等」で確認し、その内容を記録・保存することが義務付けられました。
次に当初2022年10月1日から予定されていたアルコール検知器の使用義務化は世界的な半導体不足の影響で延期されていましたが2023年12月1日から施行されています。
これにより目視等での確認に加えてアルコール検知器を用いた客観的な測定が必須となりました。
このスケジュールを正しく把握し、検知器の準備や運用フローの整備など自社の対応状況を再確認することが重要です。
アルコールチェック義務化の対象となる事業所の条件

アルコールチェック義務化は、全ての事業所が対象となるわけではありません。
道路交通法で定められた特定の条件を満たす事業所が対象となります。
具体的には、「安全運転管理者」の選任義務がある事業所が、アルコールチェックを行わなければなりません。
自社が対象事業所に該当するかどうかを正しく判断することが、法遵守の第一歩です。
ここでは、対象となる事業所の具体的な条件について解説します。

元警察官が解説!安全運転管理者の役割とアルコールチェック
「安全運転管理者」の選任が必要な事業所が対象
アルコールチェックの義務化は、道路交通法施行規則で定められた安全運転管理者を選任しなければならない事業所が対象となります。
具体的な条件は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所です。
ただし、大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。
これらの条件に該当する事業所は、安全運転管理者を選任し、事業所を管轄する警察署に届け出る必要があります。
自社の保有車両台数や乗車定員を正確に把握し、選任義務の有無を確認することが、義務化への対応の前提となります。
安全運転管理者の具体的な業務内容
安全運転管理者は、事業所における安全運転を確保するための様々な業務を担います。
主な業務内容として、運転者の適性や技能、知識の把握、運行計画の作成、危険を予測した運転や異常気象時などの安全確保に関する指導、運転日誌の記録、そして運転者に対する点呼と日常点検の実施などが挙げられます。
今回のアルコールチェック義務化に伴い、運転前後の酒気帯び有無の確認と記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持という業務が新たに追加されました。
これらの業務を適切に遂行することで、事業所全体の交通安全意識を高め、飲酒運転をはじめとする交通事故の防止を図る役割を担っています。
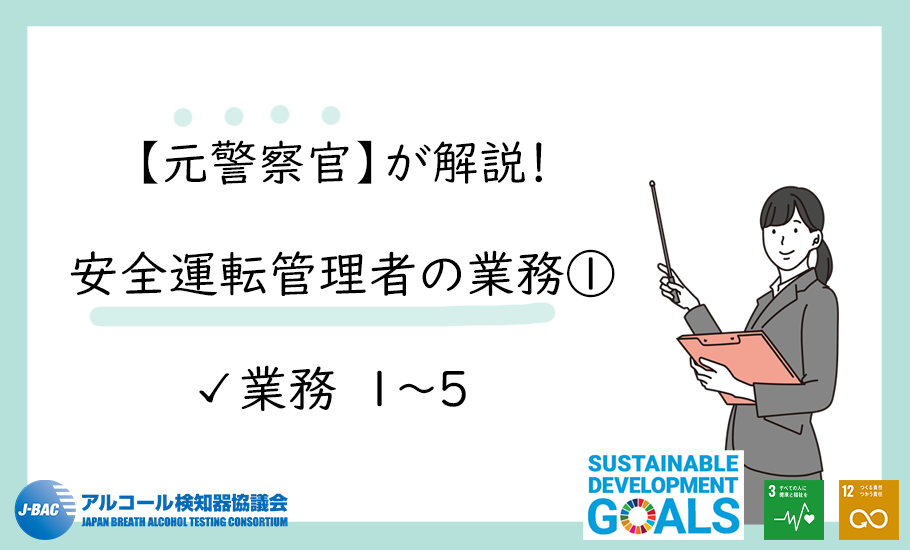
【元警察官】が解説!安全運転管理者の業務①
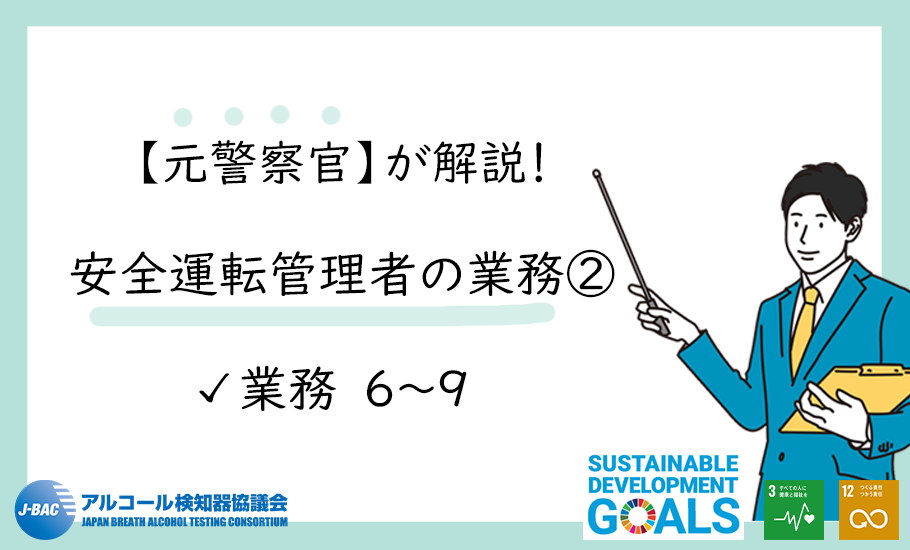
【元警察官】が解説!安全運転管理者の業務②
義務化に伴い企業が取り組むべき3つのこと

アルコールチェックの義務化に対応するため、対象となる企業は具体的な準備と運用体制の構築が求められます。
単にアルコールチェッカーを導入するだけでは不十分であり、法令で定められた要件を満たす必要があります。
ここでは、義務化に伴い企業が必ず取り組まなければならない3つの重要な項目、すなわち安全運転管理者の選任と届出、アルコール検知器の準備と管理、そして検査記録の作成と保存について、それぞれ具体的に解説していきます。
①安全運転管理者の選任と警察署への届出
アルコールチェック義務化の対象となる事業所は、まず安全運転管理者を選任し、選任した日から15日以内に事業所の所在地を管轄する警察署へ届け出る必要があります。
安全運転管理者には、年齢が20歳以上(副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)であること、そして自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験を有するなどの資格要件が定められています。
これらの要件を満たす人物を社内から選任し、必要な書類を揃えて警察署の交通課窓口に提出します。
届出が受理されて初めて、法令に基づいた管理者としての業務を開始できます。
管理者が交代した場合も同様の手続きが必要となるため、人事異動の際などは特に注意が必要です。
②アルコール検知器を準備し正常に作動する状態を保つ
2023年12月1日より、アルコール検知器を用いたアルコール検査が義務付けられました。
そのため、対象事業所はアルコール検知器を常備する必要があります。
検知器は、酒気帯びの有無を音、色、数値等で確認できるものであれば性能上の要件は問われませんが、定期的にメンテナンスを行い、常に正常に作動する状態で保持することが求められます。
センサーには寿命があるため、メーカーが定める交換時期や校正の推奨期間を把握し、適切に管理することが重要です。
故障や電池切れで測定できない事態を避けるため、予備の検知器を用意したり、定期的な点検日を設けたりするなどの対策を講じる必要があります。
③運転前後の検査記録を作成し1年間保存する
安全運転管理者は、アルコールチェックの結果を記録し、その記録簿を1年間保存する義務があります。
記録すべき項目は、確認者名、運転者名、運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号や番号、確認の日時、確認の方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合はその具体的な方法)、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項の8項目です。
これらの項目を網羅した記録簿のフォーマットを準備し、運転の都度、漏れなく記載しなければなりません。
紙の帳票で管理することも可能ですが、記入漏れや紛失のリスクを考慮すると、クラウド型の管理システムを導入して電子的に保存する方法も有効です。
アルコールチェックの義務化に伴い、管理も大変になってきます。
そういったお悩みをお持ちの方は、アルコールマネージャーのアプリで管理業務をサポートします。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要アルコールチェックの具体的な実施方法と流れ

アルコールチェックは、法令で定められた方法に則って正しく実施する必要があります。
具体的には、運転前と運転後のタイミングで、原則として安全運転管理者が対面で確認を行います。
しかし、直行直帰など対面での確認が難しいケースも想定されるため、その場合の代替方法も定められています。
ここでは、日々の業務におけるアルコール検査の具体的な実施方法と一連の流れについて、詳しく解説します。
運転前と運転後の計2回チェックを行う
アルコール検査は、運転を含む業務の開始前と終了後の計2回実施する必要があります。<br>運転前に行うのは、飲酒運転を未然に防ぐための当然の措置です。一方、運転後のチェックも義務付けられているのは、勤務中や休憩時間中の飲酒を防ぐ目的があります。
例えば、昼休憩時に飲酒し、その影響が残ったまま午後の運転業務を行うといった事態を防止するためです。
また、運転後とは、その日の運転業務が全て終了した時点を指します。
一日に複数回の運転業務がある場合、最後の運転業務が終了した後にチェックを行います。
このタイミングを社内で明確にルール化し、全運転者が遵守する体制を整えることが求められます。
安全運転管理者による対面での酒気帯び確認が原則
アルコール検査は、原則として安全運転管理者が運転者と対面で実施します。
対面での確認は、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などを直接確認できるため、なりすましや不正のリスクが低く、最も確実な方法とされています。
確認の手順としては、まず運転者の顔色などを目視で確認し、その後アルコール検知器を使用して呼気中のアルコール濃度を測定します。
安全運転管理者は、検知器の測定結果だけでなく、目視による観察結果も合わせて総合的に酒気帯びの有無を判断し、その内容を記録します。
運転者が複数いる場合は、一人ひとり順番に、確実に行う必要があります。
直行直帰や出張時など非対面での確認方法
運転者が直行直帰する場合や遠方へ出張している場合など、安全運転管理者による対面での確認が困難なケースも想定されます。
そのような場合には、対面に準ずる方法でのアルコール検査が認められています。
具体的には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させ、スマートフォンやカメラ付き携帯電話のビデオ通話機能などを利用して、運転者の顔色や声の調子、検知器の測定結果を管理者がリアルタイムで確認する方法が挙げられます。
単に電話で報告を受けるだけでは不十分であり、運転者の表情と検知器の測定値の両方を客観的に確認できる方法で実施する必要があります。
こうした非対面での運用ルールをあらかじめ整備しておくことが重要です。
アルコールチェックを怠った場合の罰則

アルコールチェック義務化に伴い、規定を遵守しない場合には様々な罰則が科される可能性があります。
罰則の対象は、飲酒運転をした運転者本人だけにとどまりません。
安全運転管理者の業務違反や、車両や酒類を提供した者、同乗者にも厳しい罰則が適用されることがあります。
ここでは、アルコールチェックを怠った場合や飲酒運転が発生した場合に、誰にどのような罰則が科されるのかを具体的に解説します。
運転者本人に科される罰則(酒酔い・酒気帯び運転)
飲酒運転をした運転者本人には、道路交通法に基づき厳しい行政処分と罰則が科されます。
アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態の「酒酔い運転」の場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、そして免許取消という重い処分が下されます。
また、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された「酒気帯び運転」では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、アルコール濃度に応じて免許停止または取消となります。
業務中の飲酒運転は、個人の問題だけでなく、企業の社会的信用を失墜させる重大なコンプライアンス違反です。
義務化を機に、社内での罰則規定の周知徹底が求められます。
安全運転管理者の業務違反に対する罰則
安全運転管理者に関する義務違反にも罰則が設けられています。
まず、安全運転管理者の選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合や、解任命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金が科されます。
また、選任はしたものの、必要な届出を怠った場合には5万円以下の罰金となります。
現状、アルコールチェックの未実施自体に直接的な罰則規定はありません。
しかし、飲酒運転が発生した場合、安全運転管理者がアルコールチェックなどの必要な業務を怠っていたと判断されれば、安全運転管理者としての解任命令が出される可能性があります。
義務化された業務を確実に遂行することが、管理者自身の責任を果たすことにもなります。
車両提供者や酒類提供者、同乗者にも罰則が適用される
飲酒運転に対する罰則は、運転者本人だけに留まりません。
運転者が飲酒していることを知りながら車両を提供した者には、運転者と同じ罰則が科されます。
企業が社用車を運転させ、飲酒運転が発覚した場合は、この車両提供者にあたる可能性があります。
また、運転者に酒類を提供した者や、飲酒運転の車両に同乗した者にも、厳しい罰則が適用されます。
酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
義務化されたチェックを怠り、結果として飲酒運転を黙認した形になれば、企業や管理者、同僚も重い責任を問われることになります。
アルコールチェック運用でよくある課題と解決策

アルコールチェック義務化に対応する上で、多くの企業が運用面の課題に直面します。
安全運転管理者の業務負担の増加や、紙の記録簿による管理の煩雑さ、さらには直行直帰時におけるなりすましといった不正のリスクなどが挙げられます。
これらの課題を放置すると、チェックが形骸化しかねません。
ここでは、アルコールチェック運用で生じがちな具体的な課題を取り上げ、その効果的な解決策について解説していきます。
管理者の負担増大や記録簿の管理が煩雑になる
アルコールチェックの義務化により、安全運転管理者の業務負担は大幅に増大します。
運転者一人ひとりに対して、運転前後に対面で確認し、その都度記録簿を作成・保管する作業は、時間と手間がかかります。
特に運転者の人数が多い事業所や、出入りの時間が不規則な事業所では、管理者の負担が深刻な問題となりがちです。
また、紙の記録簿で運用する場合、記入漏れや記載ミスが発生しやすく、ファイリングや1年間の保管、必要な際の検索にも手間がかかります。
これらの手作業による管理は非効率であるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。
業務を効率化し、確実な記録管理を実現するための工夫が必要です。
なりすましや不正のリスクをどう防ぐか
直行直帰や出張時など、非対面でアルコール検査を実施する際には、なりすましや不正のリスクが伴います。
例えば、飲酒していない同僚や家族に代わりに息を吹き込ませる、過去に撮影した検知器の測定結果の画像を送る、といった不正行為が考えられます。
このような不正を見抜けないまま運転を許可してしまうと、結果的に飲酒運転を容認することになり、重大な事故につながる恐れがあります。
電話での口頭報告のみで済ませるなど、本人確認や測定結果の客観的な確認が不十分な運用では、不正を防ぐことは困難です。
不正を防止し、アルコール検査の実効性を担保するためには、信頼性の高い確認方法を導入する必要があります。
課題解決にはアルコールチェック管理システムの導入が有効
アルコールチェック義務化に伴う様々な課題を解決するためには、クラウド型のアルコールチェック管理システムを導入することが非常に有効です。
システムを導入することで、測定結果が自動で記録・保存されるため、管理者の記録作成や保管の手間が大幅に削減されます。
また、スマートフォンアプリと連携し、測定時に顔写真を自動撮影する機能やGPSで位置情報を記録する機能を備えたシステムなら、なりすましや不正行為を効果的に防止できます。
データはクラウド上で一元管理されるため、記録の検索や確認も容易になり、管理業務全体の効率化が図れます。
コンプライアンスを確保しつつ、管理者の負担を軽減するために、システムの活用を検討する価値は高いと言えます。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要営業車のアルコールチェックに関するよくある質問

アルコールチェック義務化の運用にあたっては、様々な疑問が生じることがあります。
「自家用車を業務で使う場合はどうなるのか」「もしアルコールが検知されたらどう対応すればよいのか」といった実務上の具体的な質問は、多くの担当者が抱くものです。
ここでは、営業車のアルコールチェックに関して寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
円滑な運用体制を構築するための参考にしてください。
自家用車で業務を行う場合も対象になりますか?
従業員が個人の自家用車を業務のために運転する場合も、アルコールチェック義務化の対象に含まれます。
道路交通法における「自動車の使用」とは、企業の業務活動のために自動車を運転することを指しており、車両が社用車か自家用車かは問いません。
したがって、マイカーを業務で使用することを企業が許可し、その管理下にあると見なされる場合は、安全運転管理者の選任義務の台数計算にその自家用車もカウントする必要があります。
そして、その車両を運転する従業員に対しては、社用車と同様に運転前後のアルコールチェックを実施しなければなりません。
マイカーの業務利用に関する社内規程を整備し、チェック体制を明確にすることが重要です。
アルコールが検知されたら従業員はどうなりますか?
運転前のアルコール検査でアルコールが検知された場合、安全運転管理者は当該従業員に運転をさせてはなりません。
その日の運転業務を中止させ、代替の移動手段を手配するなどの措置が必要です。
たとえ基準値未満の微量なアルコールであっても、運転を許可することは絶対に避けるべきです。
また、アルコールが検知された事実については、就業規則に基づき厳正な処分を検討する必要があります。
出勤前の飲酒や前日の深酒が原因である場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。
処分内容については、事前に就業規則に明記し、全従業員に周知徹底しておくことが、トラブルを防ぎ、飲酒運転に対する抑止力となります。
アルコールチェッカーはどのようなものを選べば良いですか?
アルコールチェッカーは酒気帯びの有無を音、色、数値などで確認できれば法令上の性能要件は特に定められていません。
しかし精度の観点から選ぶことが重要です。
検知器のセンサーには比較的安価な「半導体ガスセンサー」とより高精度でアルコール以外のガスに反応しにくい「電気化学式(燃料電池式)センサー」の2種類があります。
業務で日常的に使用し正確なアルコール検査を行うためには電気化学式センサーを搭載したモデルが推奨されます。
また直行直帰や出張が多い場合は携帯型の検知器を事業所で複数人が使用する場合は据え置き型の検知器を選ぶなど自社の運用形態に合ったタイプを選定することが大切です。
定期的なメンテナンスやセンサー交換のしやすさも考慮に入れるべきです。
まとめ

2023年12月1日からアルコール検知器の使用が義務化され、白ナンバーの社用車を一定台数以上使用する事業所では、厳格なアルコールチェック体制の構築と運用が不可欠となっています。
アルコールチェック義務化への対応は、安全運転管理者の選任、検知器の準備と管理、運転前後のチェックと記録・保存が基本です。
これを怠った場合、運転者本人だけでなく、企業や管理者も重い責任を問われる可能性があります。
管理者の負担増大や不正防止といった運用上の課題に対しては、管理システムの導入が有効な解決策となります。
本記事で解説した内容を参考に、自社の安全管理体制を見直し、全従業員で飲酒運転根絶に取り組むことが求められます。




