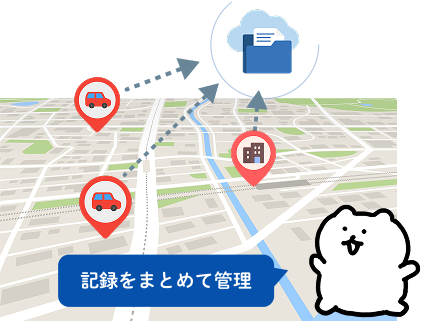飲酒検知は、事業所の車両運行における安全管理の重要な柱の一つです。
道路交通法などの法律により、一定規模以上の事業者についてはアルコール検知器の使用が義務化されており、安全運転管理者にはその確実な運用や記録管理が法律で定められた義務となっています。
アルコール検知器により計測されるアルコール濃度の数値は、運転の可否を判断する明確な基準となり、適切なチェックによって飲酒運転の未然防止が図られるため、安全運転管理の現場では不可欠なツールです。
この記事では、アルコール検知器の数値や基準、義務化への対応方法について解説しています。また、アルコール検知器の正しい使い方と選び方についてもお話しします。
ぜひ最後までご覧ください。
アルコール検知器で測定される数値について

アルコール検知器は、呼気1リットルあたりのアルコール量をミリグラム(mg/L)という単位で数値化して測定します。
通常、表示される数値は0.00mg/Lから始まり、小数点以下第二位まで正確に示されます。道路交通法における基準値は0.15mg/Lであり、呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lを超えた場合に酒気帯び運転の違反と判断されます。
一方、アルコール検知器には0.1mg/Lや0.25mg/L、0.5mg/Lといったさまざまな段階の数値が表示される製品もあり、これらの数値はアルコールの残存量を細かく確認する際の目安となります。
多くの事業所では、呼気中から少しでもアルコールが検出された場合には、基準値以下(たとえば0.15mg/L未満や0.1mg/L未満など)でも運転禁止とするケースが増えています。
これはわずかなアルコール量でも運転能力に影響を及ぼすリスクがあることから、より厳格な安全対策として実施されています。
検知器によって測定された数値は、法律上の基準値と直接リンクしているため、ドライバーはアルコール検知器を用いた呼気アルコール量の把握および管理が重要となります。
アルコール検知器の数値の特徴と見方
検知器の表示は、呼気中のアルコール量を「mg/L」という単位で具体的な数値として示され、0.00から始まる小数点第二位までの高い精度を持っています。この数値によって、呼気中に含まれるわずかなアルコールも検出できます。
道路交通法においては、アルコールの基準値が定められており、0.15mg/L以上の場合は飲酒運転とみなされて違反となります。たとえば、0.10mg/Lや0.25mg/L、0.5mg/Lなどの数値が表示された場合、それぞれ基準値との比較が重要です。
0.1mg/Lは飲酒運転の基準値未満ですが、0.25mg/Lや0.5mg/Lは明らかに基準値を超えた危険な状態です。ただし、アルコール量の数値が低くても、体質や体調、個人差によっては運転能力に影響する場合があります。
そのため、表示された数値や単位だけで判断せず、運転者の状態も併せて確認し、総合的に運転の可否を判断することが大切です。
運転時に注意すべきアルコールの基準
呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上の場合、道路交通法により酒気帯び運転として法律で厳しく禁止されています。
この基準値を超えることで、法的な罰則が科されるだけでなく、重大な交通事故を引き起こすリスクが著しく高くなります。
特に業務中に車を運転する際は、基準を下回っていてもアルコールが少しでも検出された場合には車の運転を控えることが重要です。基準値に達していなくても、個々の体調や酔いの度合いによって運転能力が低下することがあります。
飲酒後の運転は法律違反にとどまらず、社会的な信頼喪失や企業の安全管理評価にも悪影響を与えますので注意が必要です。
日常的にアルコール検知器を使って、アルコール基準をしっかりと守り、事故やトラブルを未然に防ぐ意識を持ちましょう。
酒気帯び運転の定義
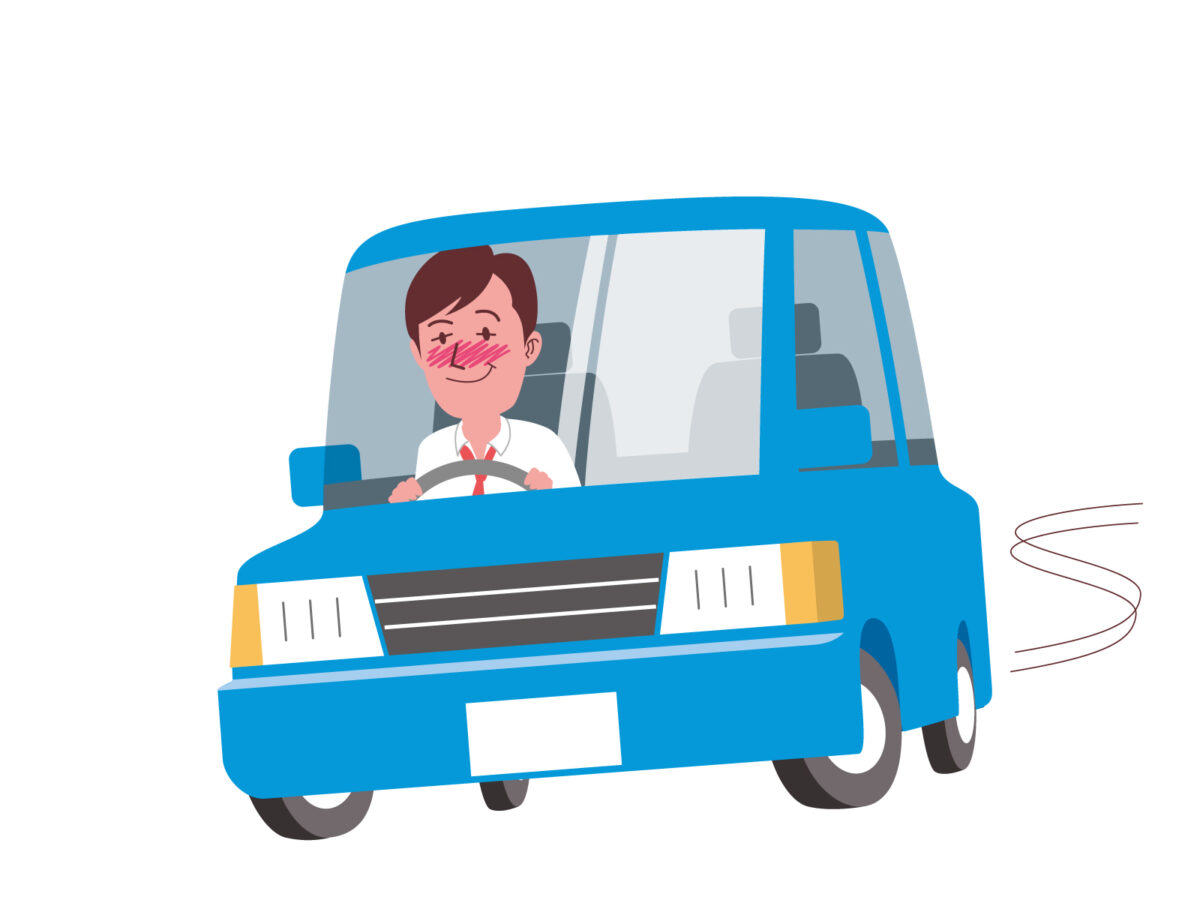
酒気帯び運転とは、道路交通法に基づき定められた基準により、体内に一定量以上のアルコールが存在した状態で運転することを指します。
具体的には、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合に酒気帯び運転と判断されます。
さらに、アルコール濃度が0.25mg/L以上の場合は、より重い処分が科されます。
酒気帯び運転は、運転能力が大きく低下し事故につながる危険性が高まるため、法律により厳しく罰せられています。飲酒直後だけでなく、アルコールが体内に残っている場合でも呼気検査で基準値を超えれば道路交通法違反となります。運転者の健康や社会の安全を守るために、この規定が重要視されています。
酒酔い運転との違い
酒酔い運転とは、酒気帯び運転よりもさらに厳しい法律上の規制が適用される運転行為です。
酒気帯び運転は呼気中のアルコール濃度に明確な基準がありますが、酒酔い運転には具体的なアルコール濃度の基準は設けられておらず、運転者の状態が法律でいう「正常な運転に著しい支障を及ぼす」と認められる場合に該当します。
たとえば、体のふらつきや会話が不明瞭になる、判断力が低下し運転操作が著しく不適切になるなどの症状が見られる場合には、酒酔い運転と判断されることが一般的です。
また、警察官は呼気検査などの数値だけでなく、目視による行動観察や体調確認も行い、総合的に酒酔い運転かどうかを判断します。酒酔い運転には免許取消しや重い罰金刑など厳格な罰則が法律で定められているため、アルコール摂取後の運転は極めて危険かつ重大な違反行為となります。
アルコール検知器を使った運転者のチェック方法

運転者の飲酒の有無を確実に確認するためには、アルコール検知器を正しく活用することが欠かせません。
点呼の際だけでなく、運転開始前後の適切なタイミングで運転者の呼気を測定し、アルコールが検知されないか確認することが求められます。単に測定結果の数値のみを基準とするのではなく、運転者の表情や言動、呼気のにおいなどを目視で確認し、さらに目視確認によって酒気帯びの兆候がないかを総合的に判断することが、安全管理には重要です。
また、検知器が正常に動作しているか事前にチェックし、誤操作を防止した上で、信頼性の高い測定を行う必要があります。
さらに、測定結果や確認内容の記録を正確に保存し、管理することで、法令遵守および運転管理体制の強化にもつながります。
安全運転管理者による点検の重要性
安全運転管理者がアルコール検知器の使用を担当することで、チェックの透明性と正確性が確保されます。
点検は単に数値を測るだけでなく、運転者の健康状態や精神的な様子について、目視確認によって異常がないか細かくチェックする役割も担っています。
安全運転管理者は、アルコール検知器の定期的なメンテナンスや校正を行い、機器が常に正しいデータを提供できるよう性能維持に努めています。
このような入念な目視や確認作業によって、運転前のリスクを未然に防ぎ、信頼できる測定結果が得られることで、アルコール検知制度全体の信頼性も向上します。また、違反者が発見された場合には、迅速な対応を行うことが求められるため、安全運転管理者の適切な目視や点検は非常に重要です。
アルコール検知器でアルコールが検知された場合の対応

検知器でアルコールが検知された場合、直ちにその運転者による運転を中止させる必要があります。
検知されたアルコール濃度が社内や法令で定める基準値を超えている場合は、飲酒が確定したものとみなし、代替の運転者の手配や運転業務の内容変更など、安全を最優先とした適切な対応が求められます。
アルコール検知結果について誤検知が懸念される場合は再検査を実施し、再検査でも基準以上のアルコールが検出された場合は、いかなる理由があっても運転の許可を出さないことが重要です。
なお、アルコール検知の手続き自体を運転者が拒否した場合、「拒否罪」となり、道路交通法などの法令違反として厳重な取り扱いが必要となります。
また、重大な違反が判明した際には、警察への通報や社内規定に基づいた処分手続きを速やかに行うことが不可欠です。アルコールの検出や検査拒否が発生した際には、会社全体で安全運転管理の徹底と法令遵守の重要性を再認識することが求められます。
飲酒運転とアルコール検知器の誤検知
アルコール検知器は、誤検知のリスクも存在します。
例えば、運転前の検査で口臭に含まれるアルコール成分や発酵食品、または口腔ケア用品の使用が一時的に検知数値を上げてしまうことが知られています。
さらに、糖尿病患者の体内で生成されるケトン体がアルコールと誤って認識されるケースもあります。
これらの誤検知を防ぐためには、検査前にうがいを行うことで口内の成分を洗い流し、より正確な数値を得ることが推奨されます。
また、検査時にはアプリや検知器の表示を目視でしっかりと確認し、異常な数値が出た場合には再検査や他の確認手段も活用しましょう。こうした工夫で、誤検知を極力減らし、運転前の正確な飲酒チェックが実現できます。
アルコール検知器の義務化と関連する基準
事業用車両の安全運転管理の強化を目的として、2023年12月1日から一般的な自家用車である「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も、アルコール検知器を使用したアルコールチェック義務化の対象となりました。
アルコールチェック義務化の対象となるのは、下記のいずれかに該当する企業です。
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
- 白ナンバー車5台以上を保持する企業
※オートバイは0.5台として換算
※それぞれ1事業所あたりの台数
出典:安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)/警視庁HP
アルコールチェックを行うタイミング
アルコールチェックの義務化により、運転開始前と終了後の両方で適切なアルコールチェックを実施することが求められています。
点呼時には運転者の顔色や発話の様子も確認し、異常が認められた場合は直ちに適切な対応を取ることが重要です。
アルコールチェックの記録についても厳格化され、測定値や日時、点検者名などの情報を1年間残さなければなりません。
最近では、アプリを活用してアルコールチェックの記録をクラウド管理する企業も増えており、違反防止や管理状況の透明化に貢献しています。
このような義務化により、企業は安全運転体制の維持や強化を行いやすくなっています。
アルコールチェックの記録方法

アルコールチェックの結果は、日時や運転者の氏名、検知器の測定数値に加え、確認時の目視による運転者の状態もあわせて正確に記録し、適切に保管することが義務付けられています。
手書きやアプリを含む電子データいずれの方式でも問題ありませんが、1年間分の記録を保存することが道路交通法施行規則第9条の10で定められています。
近年では、アプリを利用してアルコールチェックの記録をクラウド上でデータ管理する方法も普及しており、運転前後のチェック記録を効率的かつ確実に保存することが可能です。
アルコール検知器の使い方と選び方

アルコール検知器の効果を最大限に引き出すためには、正確な使用方法と適切な選定が欠かせません
使用前には検知器本体を目視で確認し、異常がないか点検することで、誤作動や故障を未然に防ぐことが可能です。さらに、日常的な点検やメンテナンスを怠らず、いつでも正常に動作する状態を維持することが重要です。
測定時の環境や運転者の状態にも配慮し、例えば強い香料や飲食直後の呼気が誤検知の原因にならないよう注意することも求められます。
最近では、測定データを専用アプリで管理できるモデルも登場しており、記録の保管や共有がより簡単になっています。
導入に際しては自社の使用目的や現場環境に適した機器を選び、信頼性と操作性の高さ、さらにアプリなどのデジタル管理機能も重視すると良いでしょう。
安全運転管理者として、アルコール検知器の選び方と使い方をしっかり把握し、呼気測定結果の記録や目視点検を日常業務の中で確実に行い、事業所全体の安全体制強化に役立てるべきです。
推奨されるアルコール検知器の選び方

アルコール検知器の選定は、アルコールチェック業務において非常に重要です。機器によって測定精度や機能面、かかるコストは様々で、正しい判断基準を持って選ぶことが必要です。
業務用として選定する際は、特に測定精度に信頼を置けるものを選ぶことが重要です。半導体式センサーの簡易的なアルコール検知器を導入してしまうと、誤検知によってさまざまな問題が生じます。
- 飲酒していないのにアルコールが検知される → 出発できない
- 飲酒しているのにアルコールが検知されない → 飲酒運転が発生するリスク
2番の、検知されない場合の誤検知は特に危険です。また、1番の飲酒していないのに検知されてしまう問題は、業務のストレス・遅延を発生させます。
このような問題に陥らないためにも、正しい基準でアルコール検知器を選ぶ必要があります。
特に、業務用では以下の項目をチェックして選ぶとよいでしょう。
- 半導体式ではなく、燃料電池式のセンサーを選ぶ(測定が正確)
- 吹きかけ式ではなく、吹き込み式を選ぶ(測定が正確)
- アプリと連動して、自動で記録される(業務ストレスが低下)
業務用のアルコール検知器をお探しなら、当社取り扱いのアルコールマネージャー®がおすすめです。
アメリカでは公的機関や警察が使用するレベルの正確なアルコール検知器で、日本でもアルコール検知器協議会の認定機器に登録されています。
また、アプリと連動して、記録を簡単に保存でき、効率的なアルコールチェックを実現します。