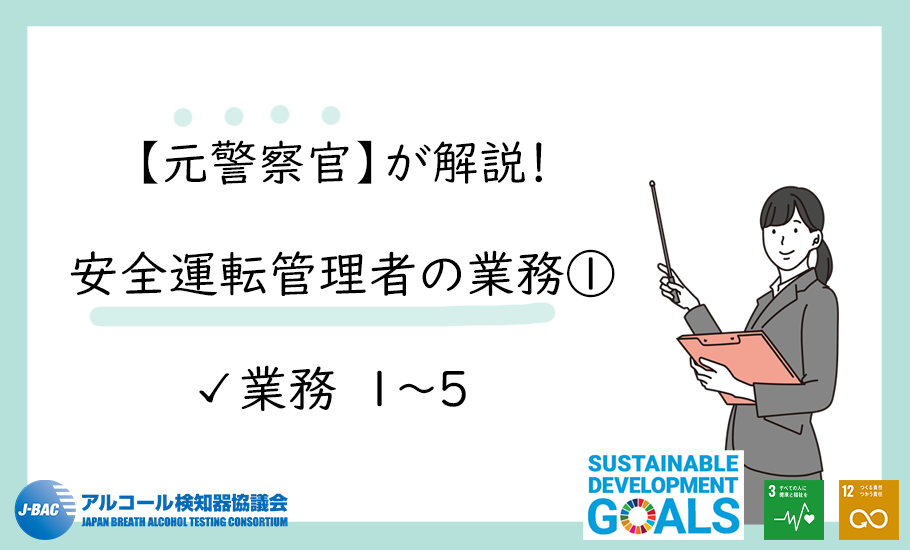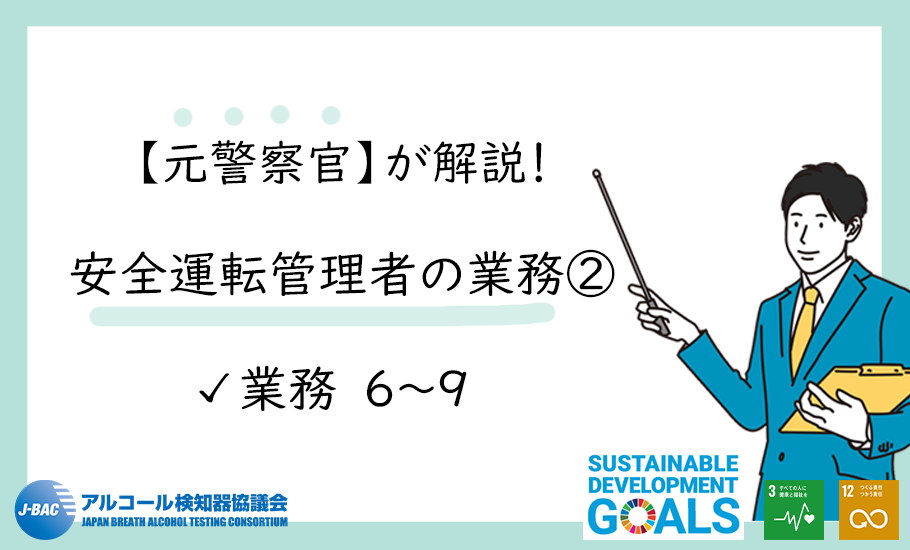事業所で一定台数以上の自動車を使用する場合、安全運転管理者を選任する義務があります。さらに車両の台数が増えると、副安全運転管理者も選任する必要があります。
副安全運転管理者とは何か、安全運転管理者との違い、そして選任義務や資格要件、必要な手続きについてわかりやすく解説します。
目次 / このページでわかること
副安全運転管理者とは

副安全運転管理者とは、事業所で使用される自動車の安全な運転を確保するため、安全運転管理者の業務を補助する役割を担う者です。
道路交通法に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、安全運転管理者とともに選任が義務付けられています。副安全運転管理者は、安全運転管理者の不在時にその業務を代行することもあり、事業所の安全運転管理体制において重要な存在と言えます。
安全運転管理者との違い
安全運転管理者と副安全運転管理者の主な違いは、選任が必要となる車両台数、資格要件、および選任人数です。安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所に選任義務が発生します。
一方、副安全運転管理者は、自動車を20台以上使用している事業所で、20台ごとに1人の選任が必要です。資格要件においても、安全運転管理者は2年以上の実務経験が必要なのに対し、副安全運転管理者は1年以上の実務経験、または3年以上の運転経験のいずれかが必要となります。業務内容自体は安全運転管理者と同様の補助的な役割を担います。
補助者との違い
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する役割を担い、その職務は道路交通法に基づいています。一方、「補助者」という言葉は、安全運転管理者や副安全運転管理者の業務を手伝う人を指すことが一般的ですが、法的な位置づけや明確な資格要件はありません。
公安委員会への届出義務があるかどうかも大きな違いです。副安全運転管理者は選任した場合に届出が必要ですが、補助者にはその義務がありません。補助者は、アルコールチェックの際の立ち会いや記録の一部をサポートするなど、社内で定めた範囲で業務を行います。適切な判断や指示ができる人が補助者を務める必要があります。
副安全運転管理者の選任が必要な場合

副安全運転管理者の選任は、道路交通法に基づき、事業所が使用する自動車の台数によって義務付けられています。
具体的には、自家用自動車を20台以上使用している事業所は、副安全運転管理者を選任しなければなりません。この選任義務の基準となる人数は、使用する自動車の台数によって異なり、20台以上39台までは1人、40台以上59台までは2人といったように、20台増すごとに1人ずつ追加で選任する必要があります。
なお、自動二輪車(原動機付自転車を除く)は、0.5台として計算します。自動車運転代行業者の場合は基準が異なり、随伴用自動車10台ごとに1人の選任が必要です。
副安全運転管理者になるための資格要件
副安全運転管理者として選任されるためには、道路交通法施行規則で定められた資格要件を満たす必要があります。
まず、年齢に関しては20歳以上であることが条件です。また、自動車の運転管理に関して1年以上の実務経験を有する者、または自動車の運転経験が3年以上であること、もしくはこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であることが求められます。
さらに、過去2年以内に公安委員会の解任命令を受けていないことや、ひき逃げ、酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転などの一定の交通違反行為をしていないことも重要な要件です。
副安全運転管理者の主な業務内容

副安全運転管理者の業務内容は、安全運転管理者の業務を補助することが主な職務です。安全運転管理者が行う多岐にわたる仕事のサポートを通して、事業所の安全運転体制を維持・向上させる重要な役割を担います。具体的には、主に以下の9つの業務を行います。
* 運転者の状況把握:運転者の適性や技能、知識、法令遵守状況を把握するための措置を実施します。
* 運行計画の作成:過労運転等の防止や安全確保のための運行計画を立てます。
* 交代要員の配置:長距離・夜間運転時の適切な交代運転者の配置を行います。
* 異常気象時などの安全確保の措置:悪天候等で安全運転に支障がある場合の必要な指示や措置を講じます。
* 点呼と日常点検:運転前の体調確認、車両の日常点検整備の実施確認、安全運転に必要な指示を行います。
* 運転前後の酒気帯び確認:運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認します。
* 酒気帯び確認の記録・保存:酒気帯び確認の内容を記録し、1年間保存します。
* 運転日誌の記録:運転日誌を備え付け、運転終了後に運転者に記録させます。
* 安全運転指導:運転者への安全運転に関する指導を行います。
これらの副安全運転者の業務は、事業所の規模が大きくなるほど量が増加する傾向にあります。
副安全運転管理者を選任したら必要な手続き

副安全運転管理者を選任した場合、所定の手続きが必要です。これは道路交通法で定められており、怠ると罰則の対象となります。
公安委員会への届出
副安全運転管理者を選任した場合、選任した日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。この届出は道路交通法によって義務付けられています。また、副安全運転管理者を解任した場合も同様に15日以内の届出が必要です。
届出に必要な書類
副安全運転管理者の選任届出には、いくつかの書類が必要です。一般的に、副安全運転管理者に関する届出書、運転管理経歴証明書(運転管理経験が1年以上の場合)、または安全運転管理者等資格認定申請書(運転経験が3年以上の場合など)、運転記録証明書(過去3年間または5年間のもの)、そして戸籍抄本、住民票の写し、または運転免許証の写しなど、本人確認ができる書類が必要となります。
ただし、必要な書類は各都道府県によって異なる場合があるため、事前に管轄の警察署や公安委員会のウェブサイトなどで確認することをお勧めします。例えば、埼玉県や千葉県、山口県、山形県など、各地域によって提出書類や様式が指定されている場合があります。
届出の提出先
副安全運転管理者の選任届出は、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課に提出します。複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所を管轄する警察署への届出が必要です。一部地域では郵送での手続きやオンラインでの申請も可能な場合がありますので、事前に管轄の警察署に確認するとよいでしょう。
交代・解任時の手続き
副安全運転管理者が交代したり、解任されたりした場合も、選任時と同様に公安委員会への届出が必要です。具体的には、交代または解任の日から15日以内に、その旨を記載した届出書を提出しなければなりません。事業所の移転や名称変更など、届出事項に変更があった場合も同様の手続きが必要です。解任時には、交付されていた副安全運転管理者証を返納する必要があります。
副安全運転管理者の法定講習
副安全運転管理者は、道路交通法に基づき、公安委員会が行う法定講習を年1回受講する義務があります。この講習は、安全運転管理者等として必要な知識や技能を習得し、安全運転管理業務の効果的な実施を図ることを目的としています。
公安委員会から講習受講の通知が送付されるので、通知内容に従って必ず受講しなければなりません。講習では、交通法規の改正内容や交通事故防止に関する知識、交通安全教育の方法などについて学びます。安全運転管理者と副安全運転管理者は合同で講習を受ける場合が多いですが、受付時間などが異なることがあるため注意が必要です。
選任しなかった場合の罰則
道路交通法では、副安全運転管理者の選任が義務付けられているにもかかわらず、その選任を怠った場合に対する罰則が定められています。
副安全運転管理者の選任義務違反には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、選任または解任したにもかかわらず、15日以内に公安委員会への届出を行わなかった場合も、5万円以下の罰金の対象となります。これらの罰則は、事業所における安全運転管理の重要性を鑑み、法令遵守を徹底させるために設けられています。
業務負担軽減のための対策

副安全運転管理者の業務は多岐にわたり、特に車両台数が多い事業所では業務負担が大きくなることがあります。このような業務負担を軽減するためには、様々な対策を講じることが有効です。
例えば、車両管理システムの導入は、運転日報の作成やアルコールチェックの記録、車両予約、運転状況の把握などを効率化し、管理者の負担を大幅に軽減することができます。
また、安全運転管理者の業務の一部を他の従業員と分担したり、外部の専門業者に委託したりすることも検討できます。社内での役割分担を明確にし、業務マニュアルを整備することも、効率的な安全運転管理に繋がります。
アルコールチェックの記録管理を軽減する
アルコールチェックとその記録は、安全運転管理者や副安全運転管理者の重要な業務の一つです。特に車両台数の多い事業所では、この記録管理の負担が大きくなりがちです。
紙やExcelでの管理は、手入力の手間や記入漏れのリスクを伴います。これらの負担を軽減するためには、システムの活用が有効です。 アルコールチェックシステムや運行管理システムを導入することで、測定結果の自動記録やクラウドでの一元管理が可能になり、管理業務の効率化と記録の正確性向上を図ることができます。
これにより、安全運転管理者はより効果的に業務を遂行できるようになります。