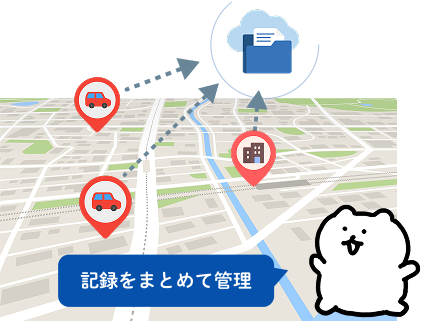目次
大規模な点呼不備で大問題に!郵便局の点呼不備問題

最近大きなニュースになった、郵便局の点呼不備問題をご存じでしょうか。
毎日新聞デジタルサイトの記事によると、日本郵便で配達員の酒気帯びの有無を確認する法定点呼業務が不適切だった問題で、国土交通省は25日、貨物自動車運送事業法に基づいて郵便局への特別監査を始めたとのこと。
配達員の飲酒点呼不備問題 国交省、郵便局へ特別監査開始 | 毎日新聞
郵便局の集荷業務を担う3188局のうち75%に当たる2391局で、乗務前後の点呼を適切に実施していなかったことが、新聞の一面記事になるほど大きな問題となっています。
また、郵便局では昨年度、横浜市の戸塚郵便局で配達員が業務中に車内でペットボトルに入れたワインを飲んで酩酊状態と判明した事案などの飲酒運転不祥事が相次いだにも関わらず、改善されていなかったと報道されています。
「面倒」意識広がり 郵便局の7割、配達員の飲酒点呼せず | 毎日新聞
この郵便局の事案を他山の石として、今こそ自社の点呼状況を見直してみましょう。
このコラムでは、なぜこのような大きな問題に発展してしまったのか考えつつ、点呼の重要性と適切な点呼方法について解説していきます。
郵便局問題は他人事じゃない!点呼と酒気帯びの確認は事業者の責務です

はじめに、この問題で取り上げられている「点呼」とは何を指すのでしょう。
郵便局は運送会社にあたりますので、今回問題となっている「点呼」とは貨物自動車運送法上の「法定点呼」のことを指しています。
法定点呼は「輸送とドライバーの安全を守る最後の砦」。
法定点呼では、運行管理者がドライバーの健康状態や酒気帯の有無、車両に異常がないかなどを確認して記録するよう定められています。
基本対面で行われることとされていますが、労働環境改善を目的に2025年4月1日からカメラやシステム機器を利用する「遠隔点呼」や「業務後児童点呼」、「IT点呼」が開始された矢先の問題発覚でした。
この法定点呼の詳細についてはトラック協会のパンフレットをご覧ください。
うちの会社は運送貨物業ではないから関係ないな、と甘く見てはいけません。
安全運転管理者にも法定点呼と同様に点呼の実施業務があり、酒気帯びの有無の確認が義務づけられているのです!
安全運転管理者の業務や酒気帯び確認の詳細については、過去コラムをご覧くださいね。
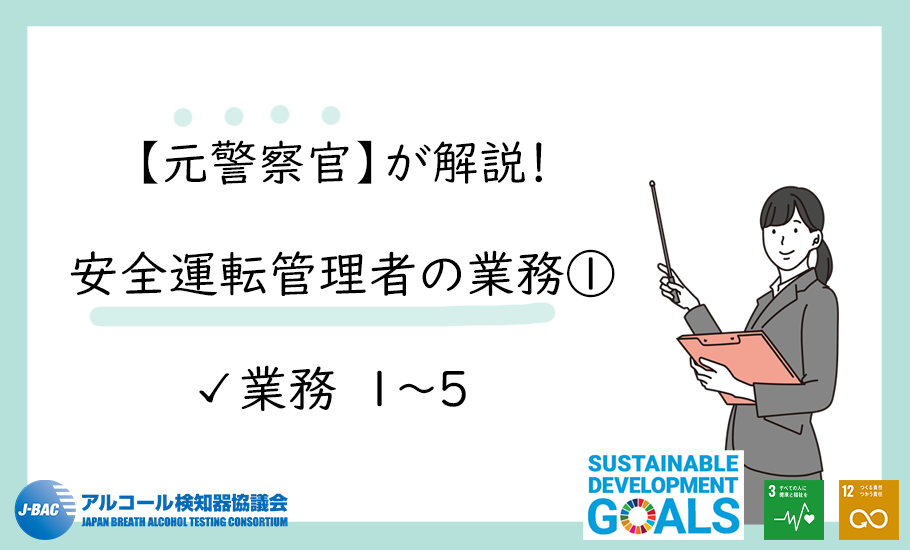
【元警察官】が解説!安全運転管理者の業務①
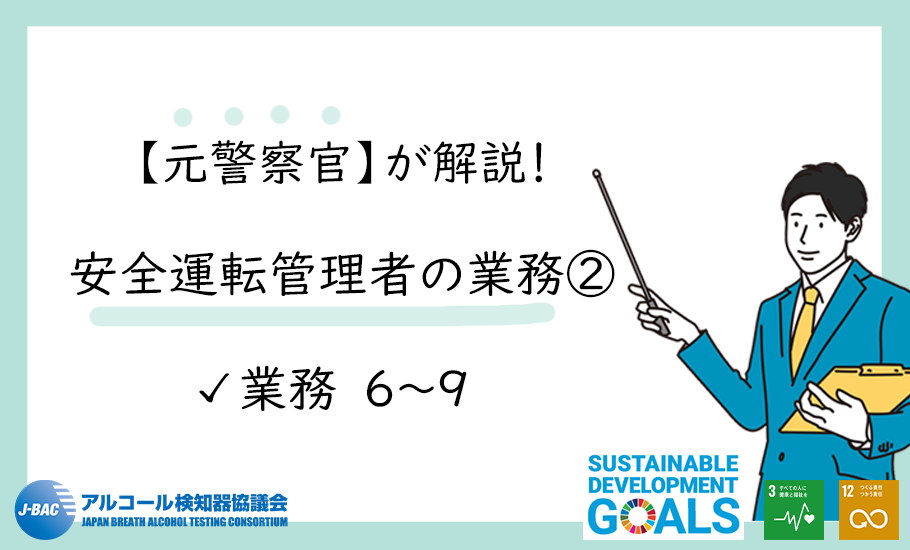
【元警察官】が解説!安全運転管理者の業務②
業種に関わらず、業務として車を運転する事業者には点呼の実施義務があるということを忘れてはいけません。
そして今、点呼の注目度は過去最高といえるでしょう。
このタイミングで是非、点呼での健康・酒気帯び確認がしっかり行われているか点検してみて下さい。
そして今後長きに渡って不備や不正が発生しないよう制度を確立させましょう。
郵便局の問題は、他人事ではありません。
運転をする全ての企業に課せられている「点呼」。
郵便局の問題点や改善方法を解説しますので、自社の点呼状況確認の参考にして下さいね。
郵便局ではなぜ点呼が行われなかった?ずさんな点呼は飲酒運転を助長します!
なぜ点呼がずさんになり実施されなくなったのか、郵便局の問題点を考えてみましょう。
日本郵便社長千田哲也氏の記者会見では、適切に点呼を実施したとの虚偽の報告が「かなりの数ある」と説明され、どうやら長年にわたって点呼不備が続いていたよう。
社内調査では
・「繁忙期は行わなかった」
・「面倒だから管理者がいる時のみやっていた」
などの回答が寄せられていて、郵便局内での意識がかなり低いこともうかがえます。
この問題の背景について、毎日新聞オンライン記事を引用してご紹介しましょう。
さすが新聞記事、完結でわかりやすいです。
≪日本郵便は不正の背景として、配達員らの間で「点呼は面倒」「勤務時間に飲酒するはずがない」といった意識が広がっていたほか、形式的に書類が整っていれば検査をされても発覚しないという安易な考えが広がっていたと分析。管理側も業務をチェックする意識が不足し、その体制も甘さがあったとした。≫
「面倒」意識広がり 郵便局の7割、配達員の飲酒点呼せず | 毎日新聞
ここから筆者が考える日本郵便の問題点は以下の3つ。
- 点呼実施状況のチェックが甘い・チェック機能がない又は機能していない
- 記録が紙書類のみで虚偽報告がしやすい
- 長年にわたるずさんな体制が原因で社内全体の意識が低い
ここからはそれぞれの問題点について、改善方法を考えてみたいと思います。
問題点① 点呼はちゃんと行われていますか?点呼にはチェックが必須です

点呼の方法は会社によって様々ですが、どのような点呼であれチェックは必須です。
ドライバーにとって、点呼は面倒なものということを忘れてはいけません。
多くの社員は「飲酒運転なんてしないのに毎日のチェックは面倒で手間」、「まるで疑われているようで不快」と感じていることでしょう。
業務の前後に行われる飲酒チェックも、昔はなかったのに追加された面倒なひと手間。
簡単に出来るなら簡単に済ませたいし、やらなくて済むならやりたくないのが本音のところです。
だからこそ、企業の上層部は点呼のチェック機能をしっかり確立させて下さい。
点呼は基本的に対面で実施するものなので、なるべく朝礼や夕礼などの時間に責任者の目の前でドライバーの健康状態と飲酒の確認をするのが理想的。
集合しての点呼が無理な場合でも、特に運転前のチェック時にはなるべく責任者が立ち会うなどして、まずは点呼を「業務の一部」として社内ルールの中に確立させましょう。
最初は毎回の確認、慣れてきたら抜き打ちでの確認にするのも良いと思います。
とにかく「上層部のチェックが全くない」という危険な状況にならないことが大切。
毎回は無理でも上層部による点呼の確認は継続的に実施して下さい。
そして「管理者がいる時だけちゃんとやる」ずさんな点呼にならないよう、点呼の確認は抜き打ちチェックの形式にして、緊張感が失われないよう気を付けましょう。
今回の問題を受けて郵便局では点呼状況をカメラで確認できるようにする再発防止策を発表していますが、この手法は確認する側の負担が大きくなるのではと筆者は感じています。
チェック機能は一部の人間に負担がよることのないよう注意が必要。
そして人間の負担を減らすために有効活用するべきなのは、機械の力ですよね。
またリモートで確認をする際には、機械の力を頼らないと不正の元になってしまいます。
機械の力を使うとはどういうことか…以下で解説します。
問題点② 紙に書くだけなら不正はたやすい!機械の力を利用して

今回の問題の大きな要因は、記録方法が紙に書く方法であったという点です。
アルコールチェックの記録を紙に書いて記録するのは安全運転管理者の業務負担が大きく、正しく継続することが難しくなります。
また、紙に書くだけならいくらでも不正できますよね。実際に日本郵便は、虚偽の報告がかなりの数あると発表しています。
特にチェックされない点呼、報告は紙に書くだけ…この状況ならば点呼不備になるのも納得です。
この問題を解決するには、「測定結果が自動で記録される」クラウドシステムと連携したアルコールチェッカーにすることがおすすめ。
アルコールチェッカーがスマホと連動し、測定時に数値とともに運転者の情報、日時、位置情報などがデータとして記録されるので、結果を手動で記録する必要がなくなります。
結果が正確に記録されるだけでなく、顔写真の撮影や位置情報も共に記録されることにより、不正や成りすましを確実に防止できます。
スマホ連動型のアルコールチェッカーを使うことで安全運転管理者の業務負担が大幅に減り、「簡単で確実に継続できる」ことから、ここ数年で多くの企業で導入が進んでいます。
「システム導入にはコストがかかりそう…」「簡単に導入できるのかな?」といった不安がある方には、
月額500円~の費用でシステム管理ができる「アルコールマネージャー®」がおすすめ。

今回の事案で会社の点呼状況を見直すならば、合わせてアルコールチェッカーの見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
また、深夜・早朝の確認や補助者の指定について、過去コラムで詳しく解説していますので、是非そちらもあわせて確認してみて下さいね。
業務の開始終了が深夜・早朝の時間帯になる場合も、人対人の確認(最低限通話で会話すること)が必要とされていますので、安全運転管理者に確認業務の負担がかからないよう、補助者を設定するなどして対応して下さい。
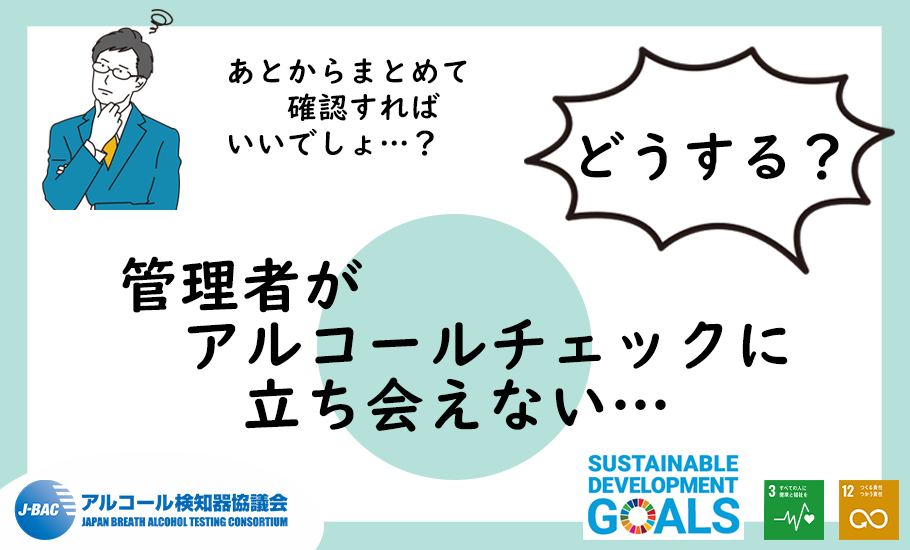
【元警察官】が解説!アルコールチェックはいつやる?深夜の連絡は?罰則は?
問題点③ ずさんな点呼が生む意識の低さ…他社の「当たり前」が出来ない会社にならないで!
最後に注目する問題点は、社内全体の意識の低さです。
日本郵便は過去にも様々な問題を起こして社内の管理体制を指摘されていますが、今回は過去の様々な件については脇に置いておきましょう。
点呼不備という一点についてのみ考えると、まず他の貨物運送業者があきれるような点呼体制と意識の低さが目につきます。
貨物運送業に携わる者にとって、点呼は「安全運送の最後の砦」。
きちんとやって当然、やらないなんて考えられないのが「点呼」です。
それほど重要なものが、郵便局ではずっと蔑ろにされてきました。
きっとチェックの甘さや虚偽報告のしやすさから、少しずつ楽な方に流れていったのでしょう。
そして一度崩れると、再び体制を整えるのは新しく始めるよりも大変です。
社員の意識改革から徹底しなければならず、今回のような大問題に発展しない限り、「ばれなければ問題ない」「これまでも問題なかったから」と楽な方に流れてしまうのが人間の心理ではないでしょうか。
そして郵便局で過去に飲酒運転事案が発生していることからもわかるように、低い意識の社風の中では、飲酒運転の種が芽吹きやすいのが事実なのです。
毎日の点呼をしっかり実施すること。
時に上層部のチェックを入れて、緊張感を保つこと。
不正も虚偽も起こらないシステムを構築して、例えリモートでも確実な実施を繰り返すこと。
毎日の点呼の確実な実施が、「面倒で不快」なものから「やって当たり前」なものへ意識を変革してくれます。
高い意識の元で交通安全の社風が構築され、結果として飲酒運転を未然に防ぐことが出来るようになるのです。
上層部から社員の一人一人まで、全員に高い安全意識が構築されるよう、毎日の点呼を抜かりなく実施しましょう。
点呼を甘くみないで!会社全体の信用問題に発展します!

今回の郵便局の点呼不備問題は、非常に影響力の大きな事案ではないかと筆者は考えます。
これまでは、大きな事故が起きてから注目を集めることがほとんどだった飲酒運転問題。
今回の事案は大問題ではありますが、飲酒運転によって人の命が奪われる前に新聞の一面記事になったという点で革新的です。
日本郵便という、日本社会にとってなくてはならない巨大組織の問題発覚だからこその一面記事なのですが、問題の内容はどの会社にとっても他人事ではないはず。
今回の点呼不備事案で、運転前の点呼や飲酒確認を怠ると会社全体の信用問題に発展することが日本社会に明確に示されました。
何度もお伝えしていますが、最後にもう一度。
今こそもう一度、会社の点呼状況を確認して下さい。
「事故を起こさなければ問題ない」という時代はとうに過ぎ去りました。
会社と社員を守るため、そして社会全体で飲酒運転を撲滅するために、点呼への意識を高めていきましょう。