2022年4月から段階的に特定の条件を満たす白ナンバー事業者にもアルコールチェックが義務化されました。
この法改正はこれまで対象外だった多くの企業にとって安全運転管理体制の見直しを迫る重要な変更点です。
本記事では白ナンバーのアルコールチェック義務化について対象となる事業所の条件や怠った場合の罰則そして企業が具体的に準備対応すべきことまで網羅的に解説します。
目次 / このページでわかること
白ナンバーのアルコールチェック義務化とは?その背景を解説

これまで、飲酒運転防止のためのアルコールチェックは、緑ナンバーの運送事業者などに限定されていました。
しかし、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、道路交通法施行規則が改正され、自家用自動車である白ナンバーを使用する事業者の一部にもアルコールチェックが義務付けられることになりました。
この背景には、社会全体で飲酒運転を根絶しようという強い意志があります。
そもそも白ナンバーと緑ナンバーは何が違うのか
自動車のナンバープレートには、自家用自動車を示す「白ナンバー」と、事業用自動車を示す「緑ナンバー」があります。
緑ナンバーは、トラックやバス、タクシーなど、他人や他社の荷物を運んだり、人を乗せたりして運賃を受け取る事業で使用される車両に交付されます。
これらの事業用自動車を運行する事業者は、輸送の安全を確保する責任が特に重いことから、以前より運転者のアルコールチェックが義務付けられていました。
飲酒運転事故をきっかけに白ナンバーも義務化の対象へ
白ナンバーへのアルコールチェック義務化の直接的な契機となったのは、2021年6月に千葉県八街市で発生した、白ナンバーのトラック運転手による飲酒運転死亡事故です。
この痛ましい事故を受け、飲酒運転根絶の社会的要請が高まり、これまで規制が比較的緩やかだった白ナンバー事業者への対策強化が急務とされました。
その結果、道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者を選任している事業者を対象として、運転前後のアルコールチェックが新たに義務付けられることになりました。
アルコールチェック義務化の対象となる事業所の条件

アルコールチェックの義務化は、全ての白ナンバー事業者が対象となるわけではありません。
道路交通法で定められた「安全運転管理者」の選任義務がある事業所が対象です。
具体的には、使用する自動車の乗車定員または台数によって判断されます。
業務で従業員のマイカーを使用する場合も、企業の管理下にあると見なされれば台数に含まれることがあります。
ただし、従業員が単に通勤にマイカーを使用しているだけの場合は対象外です。
乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
アルコールチェック義務化の対象となる一つ目の条件は、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上業務で使用している事業所です。
これには、社員送迎用のマイクロバスなどが該当します。
この条件に当てはまる事業所は、安全運転管理者を選任し、アルコールチェックを実施しなければなりません。
2022年4月からは、まず運転者の酒気帯びの有無を安全運転管理者が目視等で確認し、その内容を記録・保存することが義務付けられました。
その他の自動車を5台以上使用している(自動二輪車は0.5台で計算)
もう一つの条件は、乗車定員10人以下の自動車を5台以上業務で使用している事業所です。
営業車や配送用の小型トラックなどがこれに相当します。
台数の計算にあたり、排気量50ccを超える自動二輪車は1台を0.5台としてカウントします。
これらの車両を合計して5台以上保有する事業所も、アルコールチェック義務化の対象です。
当初、アルコール検知器の使用義務化は2022年10月に予定されていましたが、半導体不足による検知器の供給難から延期され、2023年12月1日から施行されました。

【2025年最新】社用車のアルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則も解説
いつから始まった?アルコールチェック義務化の2つの段階

白ナンバー事業者に対するアルコールチェック義務化は、企業の準備期間を考慮し、2つの段階を経て施行されました。
第一段階では目視等による確認と記録の保存が義務付けられ、第二段階でアルコール検知器の使用が必須となりました。
この段階的な施行により、事業者は順を追って体制を整備することが求められました。
これにより、より確実な飲酒運転の防止を目指しています。
2022年4月施行:目視等による酒気帯びの有無の確認
義務化の第一段階は、2022年4月1日から始まりました。
この日から、安全運転管理者は、運転者の運転前後に、顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などを目視等で確認し、酒気帯びの有無を判断することが義務付けられました。
そして、確認した日時、対象者、確認方法、酒気帯びの有無といった内容を記録し、その記録を1年間保存する必要があります。
この時点ではアルコール検知器の使用は必須ではありませんでしたが、確実な確認と記録の実施が求められました。
2023年12月施行:アルコール検知器を使用した確認の必須化
第二段階として、2023年12月1日から、目視等での確認に加え、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認が必須化されました。
これにより、主観的な判断だけでなく、機器による客観的なデータに基づいた確認が求められることになります。
企業は、呼気中のアルコールを検知し、音や色、数値などでその有無を示せる検知器を準備し、常に正常に作動するよう保守・点検を行う必要があります。
この検知器を用いた確認の運用を徹底することが重要です。
義務化に向けて企業が準備・対応すべき3つのこと
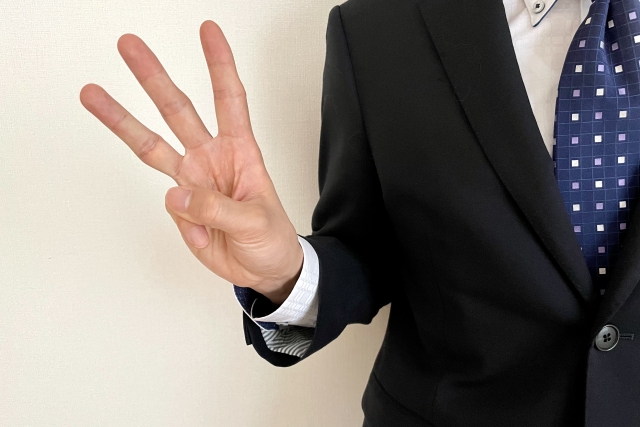
白ナンバーのアルコールチェック義務化へ対応するためには、企業はいくつかの準備を計画的に進める必要があります。
具体的には、チェックの責任者となる安全運転管理者の選任、チェックに使用するアルコール検知器の準備、そして日々の結果を確実に管理するための記録簿の整備と保管体制の構築という、大きく3つの対応が求められます。
これらを着実に実行することが、法令遵守の第一歩です。
1つ目:安全運転管理者の選任と届出を行う
アルコールチェックの実施は安全運転管理者の重要な業務の一つです。
そのため、義務化の対象となる事業所は、まず規定の要件を満たす人物を安全運転管理者として選任し、事業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。
管理者は、運転者の酒気帯びの有無を確認する責任を負います。
2つ目:アルコール検知器を準備し正常に作動する状態を保つ
2023年12月1日以降はアルコール検知器の使用が必須であるため、各事業所は必要な数の検知器を用意しなくてはなりません。
検知器は、国家公安委員会が定める、呼気中のアルコールを検知して音や色、数値などでその有無が確認できるものであれば、特定の機種に限定されません。
重要なのは、センサーの寿命や校正時期を把握し、定期的なメンテナンスを行って常に正常に作動する状態を維持することです。
なお、運転業務のない日はチェックの対象外となります。
3つ目:チェック結果を記録・保管する体制を構築する
アルコールチェックの結果は、定められた8項目を網羅した記録簿に記載し、その記録を1年間保管する義務があります。
記録媒体は紙でも電子データでも構いません。
手書きの記録簿は手軽ですが、記入漏れや紛失のリスクが伴います。
そのため、クラウド型のアルコールチェック管理システムを導入し、記録・保管業務を自動化・効率化する企業が増えています。
こうしたシステムを利用することで、管理者の負担を軽減しつつ、確実な法令遵守体制を構築できます。
アルコールチェックの義務化に伴い、管理も大変になってきます。
そういったお悩みをお持ちの方は、アルコールマネージャーのアプリで管理業務をサポートします。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要アルコールチェックの具体的な実施方法3ステップ

アルコールチェックを日々の業務に組み込むためには、明確な手順を定めておくことが重要です。
基本的な流れは、運転前後の確認、内容の記録、そして記録簿の保管という3つのステップで構成されます。
この一連のプロセスを社内ルールとして確立し、安全運転管理者と運転者の双方が理解して実践することで、スムーズで確実な運用が実現します。
ステップ1:運転前後に酒気帯びの有無を確認する
まず、運転者が車両の運転を開始する前と、業務を終了した後の両方のタイミングで、酒気帯びの有無を確認します。
この確認は、原則として安全運転管理者が対面で行います。
運転者の顔色、呼気の臭い、声の調子などを確認するとともに、アルコール検知器を使用して客観的な測定を実施します。
運転後にも確認を行うのは、昼休みなどの休憩時間中の飲酒といった、業務中の飲酒行為を防止する目的があります。
ステップ2:確認した内容を記録簿に記載する
確認が完了したら、その都度、結果を記録簿に記載します。
記録簿には、①確認者名、②運転者名、③自動車登録番号など車両を特定できる情報、④確認の日時、⑤確認の方法、⑥酒気帯びの有無、⑦指示事項、⑧その他必要な事項、という8つの項目を漏れなく記入する必要があります。
これらの項目が網羅されたフォーマットをあらかじめ用意し、記入漏れや間違いがないように運用することが求められます。
アルコールチェック記録簿についてもう少し詳しく知りたい方は下記を参考にしてみてください。

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説
ステップ3:作成した記録簿を1年間保管する
アルコールチェックの記録は、作成した日から起算して1年間保管することが法律で定められています。
保管方法は紙媒体でも電子データでも認められていますが、いつでも監督官庁などからの求めに応じて提出できるように、整理して保管しなければなりません。
電子データで保管する場合は、第三者が見てもわかるような形で保存し、容易に改ざんできないシステムを利用するなど、記録の真正性を担保する措置を講じる必要があります。
そういったアルコールチェックの管理体制に不安を抱えている方必見。
アプリと連携できるアルコールチェッカーを検討してみませんか。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要もしアルコールチェックを怠った場合の罰則と企業リスク

アルコールチェックの義務を怠った場合、企業はどのようなペナルティを受けるのでしょうか。
現時点では、チェックを怠ったこと自体への直接的な罰則は設けられていません。
しかし、それは何のリスクもないという意味ではなく、安全運転管理者の選任義務違反や、万が一飲酒運転事故を起こした場合に、企業は法的な罰則や社会的信用の失墜といった、極めて重大なリスクを負うことになります。
安全運転管理者の業務違反に対する罰則
アルコールチェックを怠ることは、安全運転管理者が本来行うべき業務を遂行していないと見なされます。
公安委員会は、安全運転管理者の業務が適切に行われていない場合に、企業に対して是正措置命令を出すことが可能です。
この命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、そもそも安全運転管理者を選任していなかった場合は、選任義務違反として50万円以下の罰金が科せられます。
つまり、間接的に罰則の対象となるのです。
運転者が飲酒運転した場合の厳しい罰則
アルコールチェックを怠った結果、従業員が飲酒運転で検挙された場合、運転者本人には厳しい行政処分と刑事罰が科されます。
酒気帯び運転でも免許停止や懲役・罰金となり、悪質な場合は一発で免許取り消しとなることもあります。
さらに、運転を指示または容認したと見なされれば、安全運転管理者や企業も処罰の対象となり得ます。
具体的には、車両を提供した者として、運転者と同じ罰則(酒酔い運転で5年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されることもあります。
企業が負うことになる社会的信用の失墜
従業員による飲酒運転やそれが原因の事故が発生した場合、企業が受けるダメージは法的な罰則だけではありません。
事故が報道されることで企業名が公になり、「安全管理ができていない会社」というネガティブなイメージが社会に広まります。
その結果、取引先からの契約解除、金融機関の評価低下、顧客離れなどを引き起こし、事業の継続が困難になるほどの経営的打撃を受ける可能性があります。
一度失った社会的信用を回復するのは極めて困難です。
アルコールチェックを正しく運用するための重要ポイント
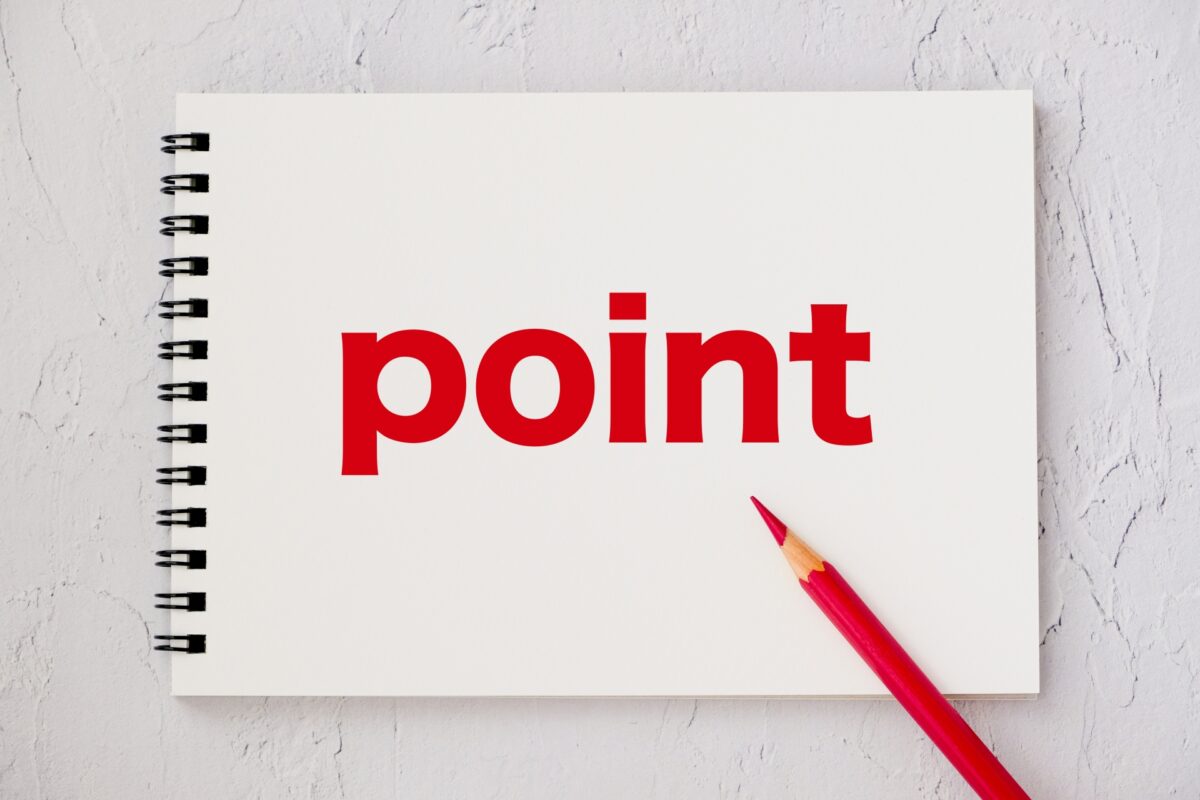
アルコールチェックの制度を形式的なものにせず、飲酒運転防止という本来の目的を達成するためには、いくつかの重要なポイントを押さえて正しく運用する必要があります。
原則である対面での確認を基本としつつ、直行直帰のような働き方にも柔軟に対応できる体制を整えること、そして、チェックの精度を担保するために検知器を常に最良の状態に保つことが不可欠です。
安全運転管理者による対面での確認が原則
アルコールチェックは、安全運転管理者が運転者と直接顔を合わせて実施する「対面確認」が基本原則です。これは、アルコール検知器の測定値だけでなく、運転者の顔色、呼気のにおい、話し方などに異常がないかを五感で確認することで、総合的に酒気帯びの有無を判断するためです。
また、なりすましなどの不正行為を防ぐ上でも対面での確認は最も確実な方法といえます。
可能な限り、この対面原則を遵守した運用体制を構築することが望まれます。
直行直帰など対面確認が困難な場合の代替策
業務形態によっては、運転者が自宅から現場へ直行したり、現場から自宅へ直帰したりするなど、事業所での対面確認が物理的に難しい場合があります。
このようなケースでは、対面確認に準ずる方法での実施が認められています。
具体的には、スマートフォンやタブレットのビデオ通話機能などを活用し、運転者の顔色や様子をリアルタイムで確認しながら、携帯型のアルコール検知器を使用させてその測定結果を映像で確認するといった方法が挙げられます。
アルコール検知器の定期的なメンテナンスを欠かさない
アルコール検知器は、常に正常に作動する状態で保持することが法律で義務付けられています。
検知器に内蔵されているセンサーは消耗品であり、使用回数や時間の経過とともに劣化し、正確な測定ができなくなります。
そのため、製品の取扱説明書に記載されているメンテナンス期間や使用可能回数を確認し、定期的なセンサーの校正や本体の交換を計画的に実施する必要があります。
各検知器の管理簿を作成し、メンテナンス履歴を記録しておくことが推奨されます。
アルコールチェックの負担を軽減する効率的な管理方法

毎日のアルコールチェックの実施、記録、保管は、安全運転管理者やドライバーにとって少なからぬ負担となります。
特に、対象となる車両やドライバーの数が多い事業所では、管理業務が煩雑になりがちです。
こうした負担を軽減し、より確実で効率的な運用を実現するために、ITツールやシステムを活用する方法が有効です。
ここでは、その代表的な方法を二つ紹介します。
クラウド型のシステムを導入するメリット
クラウド型のアルコールチェック管理システムを導入すると、記録と管理の業務を大幅に効率化できます。
ドライバーがアルコール検知器で測定した結果は、スマートフォンなどを通じて自動的にクラウドサーバーへ送信・記録されるため、手書きの記録簿への転記作業が不要になります。
管理者は、場所を問わずリアルタイムで全ドライバーのチェック状況を確認でき、記録は改ざんが困難な形で安全に保管されます。
ペーパーレス化により、保管スペースやコストの削減にもつながります。
スマートフォンアプリを活用した運用事例
近年、スマートフォンアプリと連携するタイプのアルコール検知器が普及しています。
ドライバーは、自身のスマートフォンと検知器をBluetoothで接続し、専用アプリ上で測定を行います。
多くのアプリでは、測定時に顔写真を撮影して送信する機能や、GPSで測定場所の位置情報を記録する機能が搭載されており、なりすましや不正を効果的に防止できます。
直行直帰や出張が多いドライバーの管理に適しており、より厳格かつ効率的なアルコールチェック運用を実現します。
少しでも気になった方にぜひ見てほしい。
アプリと連携できるアルコールチェックであなたの課題を解決します。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要まとめ

白ナンバーを使用する事業者へのアルコールチェック義務化は、飲酒運転の根絶に向けた重要な一歩です。
対象となる事業者は、安全運転管理者の選任、アルコール検知器の準備、そして運転前後のチェックと記録・保管といった一連の対応を確実に実施しなければなりません。
クラウドシステムなどを効果的に活用しながら、法令を遵守した管理体制を構築し、企業としての社会的責任を果たしていくことが求められます。


