2022年4月から、安全運転管理者を選任している白ナンバー事業者に対してもアルコールチェックが義務化されました。
本記事では、アルコールチェックの方法として、アルコールチェッカーの基本的な使い方から、法律で定められた正しい実施のタイミングやルール、記録すべき項目までを網羅的に解説します。
これから導入を検討している、あるいは現在の運用方法を見直したい企業の担当者に向けて、車を運転する前の必須業務であるアルコールチェックの適切な進め方を説明します。
目次 / このページでわかること
アルコールチェッカーの基本的な使い方3ステップ

前述していたようにアルコールチェッカーの測定方法は機種によって細部が異なりますが、基本的な手順や流れは共通しています。
ここでは、一般的なアルコールチェッカーの使い方を3つのステップに分けて説明します。
初めて使用する場合でも、この手順を理解しておけばスムーズに測定を進めることが可能です。
正確な測定のためには、各機器の取扱説明書を確認し、正しい流れで操作することが重要です。
①電源を入れてウォームアップを開始する
まず、アルコールチェッカー本体の電源を入れます。
電源を入れると、センサーを正常な状態に準備するためのウォームアップが自動的に開始されます。
この準備時間は機器によって異なり、数秒で完了するものから数十秒かかるものまで様々です。
ウォームアップ中は、ディスプレイにカウントダウンが表示されたり、待機を促すメッセージが表示されたりします。
この時間はセンサーのコンディションを整えるために必要な工程であり、完了するまで待たなければなりません。
準備が完了すると、電子音や画面表示の変化によって、息を吹き込める状態になったことが通知されます。
②息を吹きかけてアルコール濃度を測定する
ウォームアップが完了し、測定可能な状態になったら、機器の指示に従って息を吹きかけます。
吹き込み口や専用のマウスピースに口を近づけ、「フーッ」と音がする程度の強さで、約5秒間均一に息を吹き込み続けるのが一般的です。
息の量が足りなかったり、吹きかける勢いが弱すぎたりすると、正確な測定ができずエラー表示が出ることがあります。
途中で息継ぎをせず、一定の量をしっかりと吹き込むことが正確な測定のポイントです。
機器が息の吹き込みを検知すると、測定が開始されます。
測定中は、そのままの状態を維持します。
③ディスプレイに表示された測定結果を確認する
息の吹き込みが終わると、数秒で測定が完了し、結果がディスプレイに表示されます。
体内にアルコールが残っていなければ、測定値は「0.00mg/L」のように表示されます。
もしアルコールが検出された場合は、呼気中のアルコール濃度が具体的な数値で表示されます。
この測定結果を安全運転管理者などが確認し、記録簿に記載します。
機種によっては、数値だけでなく、ランプの色や警告音で酒気帯びの状態を段階的に知らせる機能もあります。
表示された結果は、必ず第三者が客観的に確認する必要があります。
法律で定められたアルコールチェックの正しい運用ルール

2022年4月1日から道路交通法施行規則が改正され、白ナンバー事業者のアルコールチェックが義務化されました。
対象となるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上使用し、安全運転管理者を選任している事業所です。
2023年12月1日からは、アルコール検知器の使用も義務化されています。
このルールは、飲酒運転による事故を未然に防ぐことを目的としており、対象事業者は定められた方法で厳格に運用しなければなりません。
社用車のアルコールチェック義務化について下記の記事を参考にしてください。

【2025年最新】社用車のアルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則も解説
運転前と運転後の計2回実施が基本
アルコールチェックは、運転を含む業務の開始前と終了後の計2回、実施することが義務付けられています。
これは、ドライバーが酒気を帯びていない状態で運転を開始することを保証し、さらに業務中や休憩時間における飲酒を防止するための措置です。
例えば、朝の出勤時に運転前のチェックを行い、退勤時に運転後のチェックを行うという流れが基本となります。
直行直帰や出張などで事業所に立ち寄らない場合でも、この原則は変わりません。
個々の運転ごとではなく、運転を伴うその日の業務の開始前と終了後に毎回、1日2回のチェックが求められます。
安全運転管理者が対面で目視確認を行う
アルコールチェックの確認は、原則として安全運転管理者が運転者1人ひとりに対して、対面で実施する必要があります。
これは、なりすましによる不正な申告を防ぎ、チェックの実効性を確保するためです。
安全運転管理者は、アルコールチェッカーの測定結果を確認するだけでなく、運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子などを直接目視で確認し、総合的に酒気帯びの有無を判断します。
個人の健康状態も含めて確認することで、より安全な運行管理を実現できます。
このため、測定は機械的に行うのではなく、管理者と運転者とのコミュニケーションを伴う重要な業務と位置づけられています。
対面が難しい場合は電話やカメラで確認する
直行直帰や遠隔地での勤務など、事業所での対面確認が物理的に難しい場合には、それに準ずる方法での確認が認められています。
具体的には、カメラ、携帯電話、スマホなどを利用したビデオ通話が挙げられます。
この方法では、安全運転管理者がリアルタイムで運転者の顔色や声の調子を確認し、同時にアルコールチェッカーを使用している様子と測定結果の数値をカメラ越しに確認します。
電話のみで声だけを確認する方法は、運転者の表情やチェッカーの測定値が確認できないため、不十分とされています。
LINEなどのアプリのビデオ通話機能も活用できますが、なりすましなどを防ぐためにも、確実に本人確認と測定結果の目視ができる方法を選ぶ必要があります。
アルコールチェックで記録すべき8つの必須項目

アルコールチェックを実施した際は、その内容を記録簿に記載し、保管することが法律で義務付けられています。
記録すべき必須項目は全部で8項目あり、これらの内容に漏れがあると指導の対象となる可能性があります。
安全運転管理者は、チェックのたびにこれらのリストに沿って正確に記録し、適切に管理しなければなりません。
記録には、測定結果だけでなく、確認者や運転者の情報、さらには運転者への指示事項も含まれます。
記録簿は1年間保管する義務がある
作成したアルコールチェックの記録簿は、記録した日から起算して1年間保管することが道路交通法施行規則で定められています。
保管形式は紙媒体のほか、改ざん防止措置が講じられていれば電子データでの保存も認められています。
日々の記録を確実に保管し、警察官から提示を求められた際には、速やかに提出できるようにしておく必要があります。
近年では、アルコールチェックの結果をクラウド上で管理できるアプリやシステムも多く提供されています。
これらのツールを活用することで、記録の自動化、保管・管理の効率化、記録漏れの防止が期待できます。
無料のテンプレートやアプリも存在しますが、自社の運用体制やセキュリティ要件に合ったものを選ぶことが重要です。

【テンプレートあり】アルコールチェック記録簿に必要な項目と記入例、保存期間について解説
正確な測定のために!アルコールチェック実施前の注意点
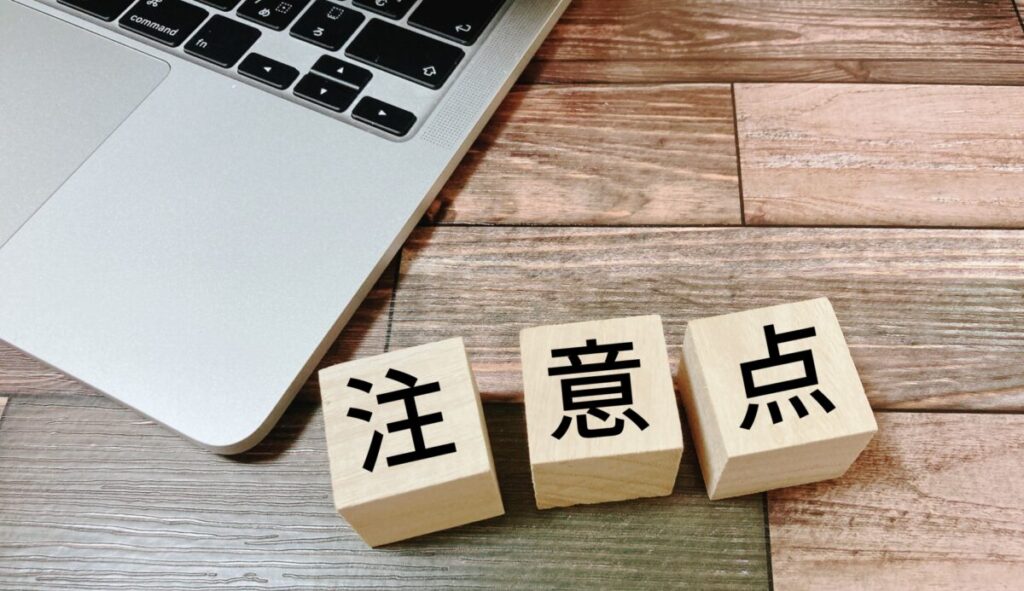
アルコールチェッカーは微量なガスを検知する精密機器であるため、飲酒していなくても、口腔内の状態や直前の食事内容によってアルコール反応が出てしまうことがあります。
このような誤検知を避けるためには、測定前にいくつかの注意点を守る必要があります。
正確なチェックを行わなければ、運転できるはずのドライバーが運転できなくなるなどの問題が発生する可能性もあります。
ここでは、信頼性の高い測定を実施するための具体的な注意点について解説します。
測定直前の飲食や喫煙は避ける
アルコールチェッカーは、アルコール以外の物質にも反応することがあります。
例えば、パンや味噌、納豆などの発酵食品、キムチ、栄養ドリンク、ノンアルコール飲料などには、微量のアルコールが含まれている場合があり、これらを摂取した直後に測定すると、センサーが反応する可能性があります。
また、喫煙直後は、タバコの煙に含まれる一酸化炭素などのガスにセンサーが反応してしまうことがあります。
これらの誤検知を避けるため、飲食や喫煙の後は最低でも15分から20分ほど時間を空け、さらに水でうがいをしてから測定することが推奨されています。
口腔ケア用品を使った直後の測定はNG
歯磨き粉や液体歯磨き、マウスウォッシュなどの口腔ケア用品には、殺菌成分としてアルコールが含まれている製品が多くあります。そのため、これらの製品を使用してすぐにアルコールチェックを行うと、飲酒していなくてもアルコールが検出される原因となります。
特に、ミント系のフレーバーが強い製品は、センサーが反応しやすい傾向にあります。
誤検知を防ぐためには、口腔ケア用品を使った後、必ず水で十分に口をすすぎ、15分以上の時間を置いてから測定に臨むようにしてください。
あらかじめ、アルコール成分が含まれていないノンアルコールの口腔ケア用品を使用することも有効な対策となります。
前日に深酒した場合は特に注意が必要
前日の夜に深酒をした場合、翌朝の起床時に自分では酔いが覚めたと感じていても、体内にアルコールが残っているケースは少なくありません。
睡眠を取ったとしても、アルコールの分解には時間がかかり、体質やその日の体調、飲酒量によって分解速度は大きく異なります。
「もう大丈夫だろう」という自己判断は非常に危険です。
アルコールチェックを行い、チェッカーが反応しないことを客観的な数値で確認してから運転を開始しなければなりません。
少しでもアルコールが検出された場合は、運転を中止させる必要があります。
運転者の感覚だけに頼らず、必ず測定器で確認することが重要です。
自社に合ったアルコールチェッカーの選び方

アルコールチェック義務化に伴い、多種多様なアルコールチェッカーが市販されています。
機器によってセンサーの性能、価格、形状、付加機能などが大きく異なるため、自社の事業規模や運用方法、ドライバーの働き方に合った製品を選ぶことが重要です。
適切なチェッカーを選定することは、法令遵守はもちろん、日々のアルコールチェック業務を円滑かつ正確に進めるための第一歩となります。
ここでは、チェッカー選定の際に比較検討すべきポイントを解説します。
センサーの種類(半導体式/電気化学式)で選ぶ
アルコールチェッカーの心臓部であるセンサーには、主に「半導体ガスセンサー式」と「電気化学式(燃料電池式)」の2種類が存在します。
半導体ガスセンサー式は、比較的安価でコンパクトな製品が多いですが、アルコール以外のガス(タバコの煙や食品の匂いなど)にも反応しやすいという特性があります。
一方、電気化学式センサーは、呼気に含まれるアルコール成分と化学反応を起こして測定するため、アルコールへの選択性が高く、より正確な測定が可能です。
価格は高価になる傾向がありますが、精度や耐久性を重視する場合や使用頻度が高い事業所には、電気化学式が適しています。
使い方に合わせた形状(携帯型/据置型)で選ぶ
アルコールチェッカーの形状は、大きく「携帯型」と「据置型」に分けられます。
携帯型は小型で軽量なため、持ち運びに便利です。
そのため、ドライバーが各自で携行し、直行直帰や出張先でのチェックに使用するのに適しています。
簡易なモデルから高精度なものまで価格帯も様々です。
一方、据置型は、事務所の出入り口などに常設して使用するタイプです。
測定結果の自動記録・印刷機能や、ICカードリーダーによる個人認証機能など、管理業務を効率化する高機能なモデルが多いのが特徴です。
主に、複数のドライバーが同じ拠点から出発するような事業所での利用に向いています。
国家公安委員会の認定品(J-BACマーク)を選ぶ
アルコールチェッカーを選ぶ上で、信頼性を判断する一つの基準となるのが、第三者機関による認定です。
国家公安委員会が定める技術上の要件を満たした機器は、その旨が表示されています。
また、アルコール検知器協議会(J-BAC)という団体が、一定の品質基準を満たした製品に対して「J-BACマーク」を付与しています。
法律上、これらの認定品の導入が必須とされているわけではありませんが、客観的に性能が保証された信頼性の高い機器を選ぶことは、正確なアルコールチェック運用のために非常に重要です。
製品選定の際には、こうした認定の有無を確認することが推奨されます。
弊社では、警察でも使用されているアルコール検知器と同じ「燃料電池式センサー」を搭載したアルコールチェッカーを使用しています。
また、アプリと連携することで煩雑なアルコールチェック管理業務を軽減!
詳しくは下記のリンクをクリックしてみてください。
アプリで簡単に管理できる
アルコールチェッカー

- 業界最安の料金プラン
- シンプルな操作性
- 記録を自動化
↓ 詳しくはこちらをチェック
アルコールマネージャーのサービス概要精度を保つためのアルコールチェッカー点検・保守

アルコールチェッカーは、使用を続けることでセンサーが劣化し、測定精度が低下していきます。
そのため、道路交通法施行規則では、アルコール検知器を「常時有効に保持すること」が義務付けられています。
これは、定期的なメンテナンスや校正を行い、常に正常に作動する状態を維持しておく必要があるということです。
ここでは、チェッカーの精度を保つために欠かせない、日々の点検と保守管理のポイントについて説明します。
毎日の使用前に行うべき動作確認
安全運転管理者は、アルコールチェッカーを使用する前に、毎日その状態を確認する義務があります。
主な確認項目は、電源が正常に入るか、本体に損傷がないかといった外観のチェックです。
加えて、実際に息を吹きかけてみて、アルコールを摂取していない人が測定した場合に、アルコールが検出されない(数値が0.00mg/Lと表示される)ことを確認します。
この日常点検を怠ると、機器の故障に気づかないまま測定を続けてしまい、不正確な結果に基づいて運行を許可してしまうリスクがあります。
異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、修理や交換を行う必要があります。
センサーの使用期限や使用回数の上限を守る
アルコールチェッカーのセンサーには、製品ごとに性能を維持できる使用期限や測定回数の上限が定められています。
この寿命はセンサーの種類によって異なり、例えば半導体ガスセンサー式では購入後1年または測定回数1,000〜5,000回程度、電気化学式センサーでは1〜2年または数千回〜数万回が目安とされています。
この上限を超えて使用を続けると、センサーが劣化して正確な測定値が得られなくなります。
製品の取扱説明書で定められた期限や回数に達した場合は、メーカーに依頼してセンサーを交換するか、機器本体を買い替えるなどのメンテナンスが不可欠です。
まとめ
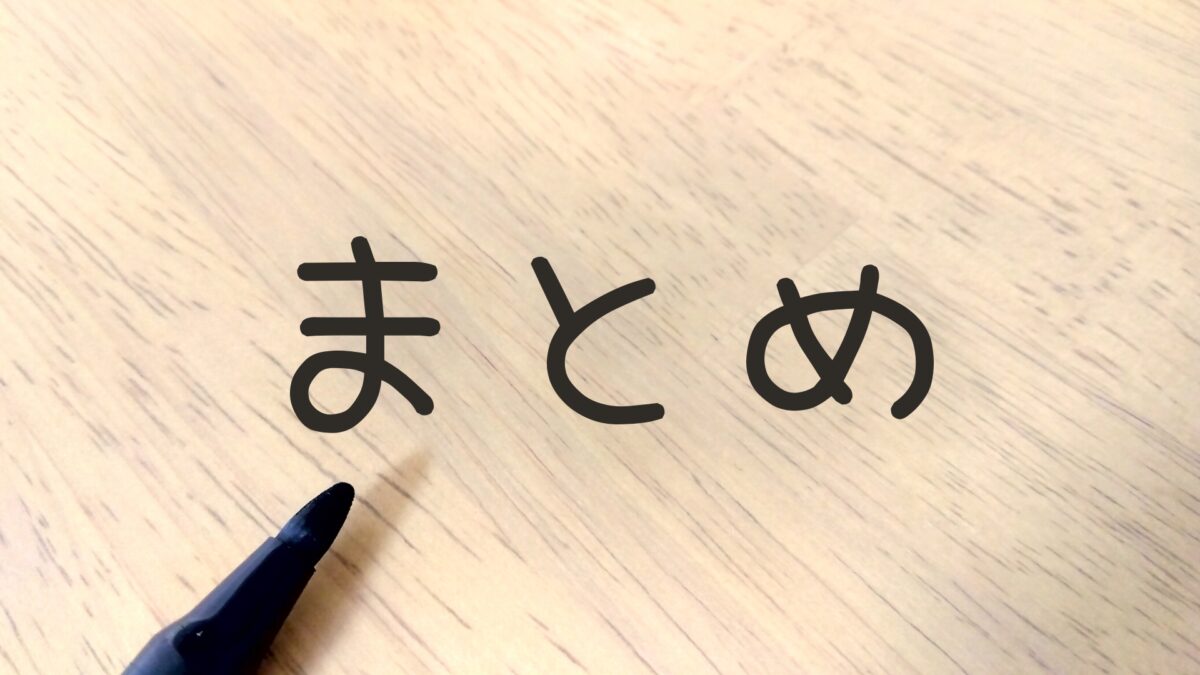
白ナンバー事業者におけるアルコールチェックの義務化に対応するためには、アルコールチェッカーの正しい使い方を理解し、定められたルールを遵守した運用体制を構築する必要があります。
チェックは運転を含む業務の開始前と終了後の1日2回、安全運転管理者が対面またはカメラ等で目視確認を行うのが原則です。
測定結果は、確認者名や日時を含む8つの必須項目を記録し、その記録簿を1年間保管しなければなりません。
チェッカーの選定では、自社の運用に合ったセンサーの種類や形状を選び、精度を維持するための日常点検や定期的なメンテナンスを確実に実施することが、制度の適切な運用につながります。


