安全運転管理者講習は、企業や事業所における安全運転管理者が、道路交通法に基づき義務付けられている講習です。
この講習は、安全運転管理業務に必要な知識や技能を習得し、従業員の交通事故防止、企業の社会的責任を果たす上で不可欠なものとなっています。本稿では、安全運転管理者講習の具体的な内容、受講方法、費用、関連する法令や義務、罰則まで、幅広く解説します。
目次 / このページでわかること
安全運転管理者講習の概要
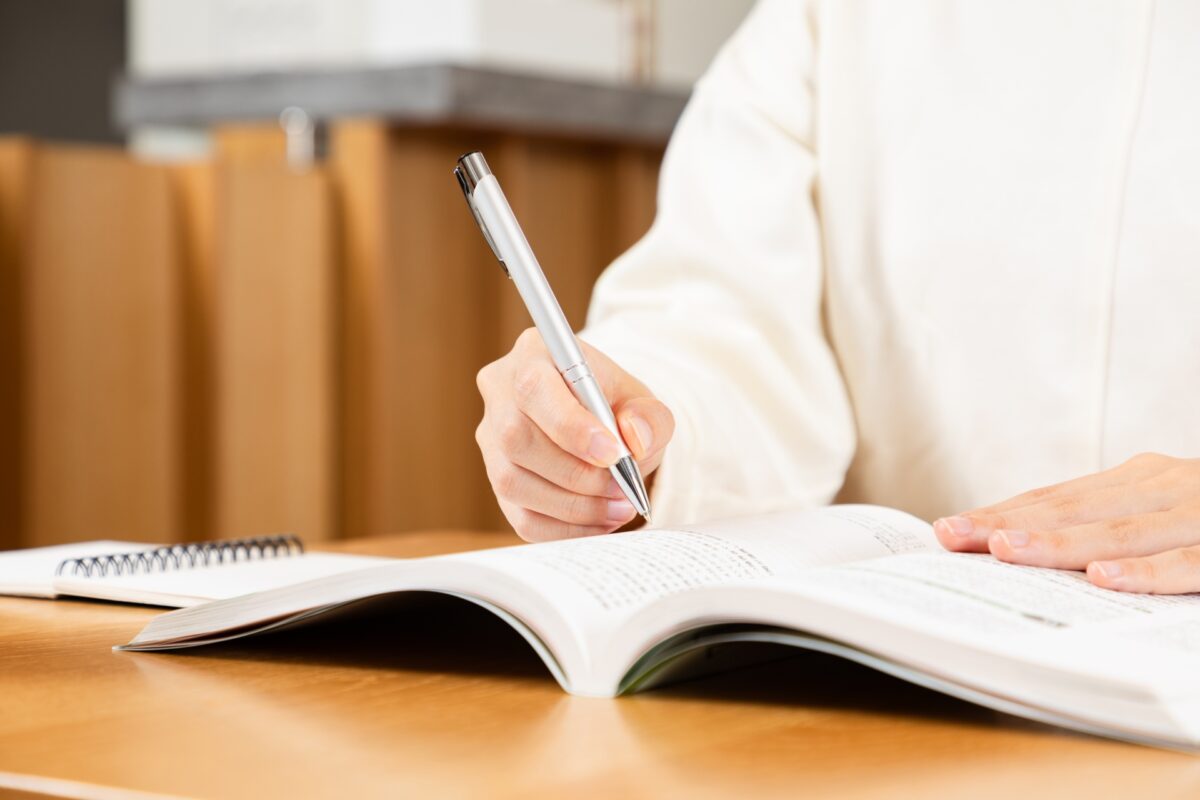
安全運転管理者講習とは、道路交通法に基づき事業者が選任する安全運転管理者に対して義務付けられている法定講習であり、安全運転管理業務に必要な知識を習得するためのものです。講習の内容は、道路交通法の改正や交通情勢の変化に対応し、常に最新の情報が盛り込まれています。
安全運転管理者講習の必須性
安全運転管理者講習は、道路交通法第108条の2第1項第1号に基づき、安全運転管理者に義務付けられている法定の講習です。この講習は、事業用自動車を保有する事業所において、従業員の安全運転を確保するために不可欠な知識と技能を習得することを目的としています。選任された安全運転管理者は、公安委員会から講習の通知を受け、必ず受講する法律上の義務を負っています。
受講対象者の範囲
安全運転管理者講習の受講対象者は、事業所で選任された安全運転管理者および副安全運転管理者です。これには、新たに選任された者だけでなく、既に選任されている者も含まれます。継続的に安全運転管理業務の知識を更新し、安全運転管理体制の維持・向上に努めることが求められます。
講習にかかる費用
安全運転管理者講習にかかる費用は、地域によって異なりますが、一般的には講習手数料として設定されています。例えば、福岡県では7,800円、神奈川県では6,700円とされています。
これらの手数料は非課税であり、消費税はかかりません。受講料は講習当日、受付で現金にて支払うことが一般的です。金額は各都道府県の公安委員会が定めるため、事前に確認することが重要です。
当日持参するもの
安全運転管理者講習の当日には、指定された持ち物を持参する必要があります。具体的には、公安委員会から送付された「法定講習通知書」や「講習受講票」、筆記用具(鉛筆、ボールペン)、そして講習費用を準備します。また、身分証明書や、必要な場合は眼鏡なども忘れないようにしましょう。
特に指定の服装はありませんが、長時間にわたる講習となるため、動きやすく楽な服装が望ましいです。講習で使用する資料は会場で配布されることが一般的ですが、事前に案内がある場合はそれに従いましょう。
安全運転管理者講習の日程

安全運転管理者講習は、各都道府県の公安委員会が定めた日程で実施されます。受講者は、自身の都合に合わせて日程を選択し、事前に予約する必要がある場合もあります。講習は年間を通じて複数回開催されるのが一般的です。
一般的な開催時間
安全運転管理者講習の開催時間は、道路交通法施行規則により、安全運転管理者で6時間以上10時間以内、副安全運転管理者で4時間以上8時間以内と定められています。一般的には午前10時頃から午後5時頃までの約6時間(休憩時間を除く)で行われることが多いです。
この時間内には、講義だけでなく、休憩時間も含まれます。講習内容は多岐にわたるため、午前中と午後に分けて行われ、昼休憩も設けられています。具体的な時間割は、各都道府県の公安委員会や講習実施機関によって異なる場合がありますので、事前に配布される案内やホームページで確認することが重要です。
各都道府県の開催日程
安全運転管理者講習の開催日程は、各都道府県の公安委員会によって定められ、年間を通じて複数回開催されます。例えば、福岡県では、令和6年度の講習日程が公表されており、福岡市や北九州市など、複数の会場で実施されます。神奈川県では、公益財団法人神奈川県安全運転管理者会が講習を実施しており、令和6年度の年間日程が公式サイトで確認可能です。東京都の場合、警視庁のウェブサイトで講習日程が案内されています。その他、埼玉、大阪、兵庫、千葉、愛知、茨城、栃木、福島、宮城、京都、岡山、広島、新潟、沖縄、滋賀、熊本、宮崎、富山、山口、青森、静岡、高知、佐賀、和歌山、大分、奈良、山梨、岩手、徳島、愛媛、福井、鹿児島、山形、三重、北海道、秋田、長野、香川、長崎、鳥取など、全国各地で講習が実施されており、それぞれの地域を管轄する公安委員会や安全運転管理者協会などのウェブサイトで最新の日程を確認できます。多くの場合、令和6年や令和7年の日程が順次公開されていますので、受講を希望する際には早めに確認し、必要な場合は予約手続きを進めることが肝要です。
講習内容の詳細
安全運転管理者講習の内容は、多岐にわたり、安全運転管理業務を遂行する上で必要な専門知識や最新の法令に関する情報が網羅されています。主な講習内容としては、道路交通法等の法令改正に関する事項、交通安全教育の手法、交通事故防止対策、危険予測・回避に関する知識などが挙げられます。
飲酒運転防止対策や、最近ではアルコールチェック義務化に伴う知識の習得も重要な項目となっています。また、事業所の安全運転管理規程の作成や見直しに関する指導、運転適性検査の結果を活用した個別指導の方法等、実務に役立つ具体的な内容も含まれています。
受講までのプロセス

安全運転管理者講習を受講するまでのプロセスは、まず事業所で安全運転管理者を選任し、その旨を公安委員会に届け出るところから始まります。選任が完了すると、公安委員会から法定講習の通知書が送付され、それに基づいて講習の受付を行い、受講することになります。事前の予約が必要な場合もあるため、通知書の内容をよく確認し、必要な手続きを進めることが重要です。
安全運転管理者選任の届け出
安全運転管理者を選任したら、速やかに事業所の所在地を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。これは道路交通法で定められた義務であり、選任後15日以内に手続きを完了させなければなりません。
届け出には、安全運転管理者等に関する届出書や、管理者の資格を証明する書類などが必要です。この届け出が完了しないと、法定講習の通知が届かない場合がありますので、忘れずに行うことが重要です。
法定講習通知書の送付
安全運転管理者の選任届出が完了すると、管轄の公安委員会から法定講習の通知書が送付されます。この通知書には、講習の開催日時、場所、持ち物、費用などが記載されています。多くの場合、通知書が送られてきた時点で、すでに講習日が指定されていることもあります。
もし都合が悪い場合は、記載されている連絡先に問い合わせて日程変更の可否を確認する必要があります。この通知書は講習の受講に必要となる重要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管しましょう。
講習の受講
法定講習通知書に記載された日時と場所に、必要書類と受講費用を持参して講習を受講します。会場での受付を済ませ、指定された席に着席します。講習は、座学形式で行われることがほとんどで、講師による説明や配布資料に基づいて進められます。
事前に予約が必要な講習会場もありますので、通知書や各都道府県の安全運転管理者協会等のウェブサイトで詳細を確認し、適切な手続きを済ませてから会場に向かうことが大切です。
受講における留意事項

安全運転管理者講習を受講する際には、いくつかの留意事項があります。これらは講習をスムーズに受講し、その効果を最大限に引き出すために重要です。例えば、代理人による受講は認められていないこと、講習の途中退席は原則禁止であることなどが挙げられます。
代理人による受講の不可
安全運転管理者講習は、選任された安全運転管理者本人または副安全運転管理者本人が受講することが義務付けられています。代理人による受講は一切認められていません。これは、講習内容が安全運転管理業務の遂行に直結する専門的な知識であるため、本人が直接受講し、その内容を理解することが重要であるためです。もし、やむを得ない事情で本人が受講できない場合は、事前に講習実施機関に連絡し、対応を相談する必要があります。
途中退席の禁止
安全運転管理者講習は、原則として途中退席は禁止されています。これは、講習内容が連続性を持って構成されており、途中で退席すると重要な情報が欠落する可能性があるためです。また、講習の修了には全課程の受講が必須となる場合が多く、途中退席した場合は修了が認められない可能性があります。緊急の用事がある場合は、事前に講師や受付担当者にその旨を伝え、指示に従うようにしましょう。
会場駐車場の利用について
安全運転管理者講習の会場には、駐車場が併設されていない場合や、駐車場の数が限られている場合があります。特に都市部の会場では、公共交通機関の利用を推奨していることが多いです。事前に会場の案内を確認し、駐車場が利用できるか、利用できる場合の料金や予約の必要性を確認しておくことが重要です。駐車場が利用できない場合は、近隣の有料駐車場を探すか、電車やバスなどの公共交通機関を利用することを検討しましょう。
講習を受けなかった場合の措置
安全運転管理者は、年に1回、公安委員会が実施する法定講習を受講することが義務付けられています。この講習を受講しなかった場合でも、直接的な罰則は道路交通法に明記されていません。ただし、安全運転管理者の選任義務違反や、選任・解任の届出義務違反などには罰則が科せられます。
具体的には、安全運転管理者の未選任や、選任・解任の届出を怠った場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、安全運転管理者に対する解任命令や是正措置命令に従わない場合にも罰則が適用されることがあります。法定講習は、安全運転管理者が業務を適切に遂行するために重要な知識を学ぶ場であるため、受講が強く推奨されています。
安全運転管理者制度の全体像

安全運転管理者制度とは、事業活動における交通事故防止を目的として、一定台数以上の自動車を使用する事業所に安全運転管理者の選任を義務付ける制度です。この制度は、事業者が自社の安全運転管理体制を確立し、従業員の交通事故防止に積極的に取り組むことを促進するためのものです。安全運転管理者は、日常の安全運転指導や車両管理、運転者の状況把握など、多岐にわたる業務を通じて事業所の交通安全に貢献します。
安全運転管理者制度の定義
安全運転管理者制度とは、道路交通法に基づき、一定台数以上の事業用自動車を保有する事業所に対して、安全運転管理者を選任することを義務付ける制度です。これは、事業所における従業員の交通事故防止と安全運転の確保を目的としています。選任された安全運転管理者は、車両の管理、運転者の指導、運行計画の作成など、多岐にわたる業務を通じて、事業所の交通安全を統括する役割を担います。
企業が管理者を選任する理由
企業が安全運転管理者を選任する理由は、道路交通法によってその義務が課せられているからです。この法律に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所は、安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る必要があります。
選任することで、企業は従業員の安全運転を組織的に推進し、交通事故を未然に防止する体制を構築することができます。これにより、交通事故による企業イメージの低下や経済的損失を防ぎ、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。

【元警察官が解説!】アルコールチェック義務化とは?企業が行うべき対応まとめ
安全運転管理者の選任義務
安全運転管理者の選任義務は、道路交通法によって定められており、一定の要件を満たす事業所は必ず安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る必要があります。これは、事業所の車両を使用する従業員の安全を確保し、交通事故の防止を図る上で非常に重要な役割を担います。
選任義務の対象事業所
安全運転管理者の選任義務の対象となる事業所は、乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所、またはその他の自動車を5台以上(自動二輪車(50cc超)は1台を0.5台として計算)使用している事業所です。これらの台数には、他社からリースしている車両も含まれます。営業所や支店など、独立した事業活動を行っている場所ごとに選任が必要となります。
必要な管理者の人数
事業所で必要な安全運転管理者の人数は、その事業所が使用する自動車の台数によって決まります。自家用自動車を20台以上使用している事業所では、20台ごとに1人の副安全運転管理者を選任する必要があります。つまり、自動車が20台未満であれば安全運転管理者1人で足りますが、20台以上であれば安全運転管理者1名と副安全運転管理者1名、40台以上であれば安全運転管理者1名と副安全運転管理者2名といった形で、20台ごとに副安全運転管理者を1名追加選任する必要があります。
副安全管理者の選任要件
副安全運転管理者の選任要件は、20歳以上であり、自動車の運転管理に関して1年以上の実務経験を有する、または自動車の運転経験が3年以上であることが求められます。また、公安委員会がこれらと同等以上の能力を有すると認定した人も要件を満たします。
過去2年以内に、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反などの交通違反の下命や容認を受けた者、または自動車使用制限命令違反を受けた者、妨害運転をした者は要件に該当しません。
複数の事業所を持つ場合の注意点
複数の事業所を持つ企業の場合、各事業所が安全運転管理者の選任義務の対象となる可能性があります。つまり、それぞれの事業所で、乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上、またはその他の自家用自動車を5台以上使用している場合は、個々の事業所ごとに安全運転管理者を選任し、届け出る必要があります。一括して本社で管理するのではなく、各事業所の状況に応じて適切に選任を行うことが重要です。
選任後の届け出の必要性
安全運転管理者を選任した後、その旨を事業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。この届け出は、選任後15日以内に行うことが道路交通法で義務付けられています。届け出を怠ると、罰則の対象となる可能性がありますので、選任が完了したら速やかに手続きを済ませることが重要です。
安全運転管理者を選任しなかった場合の罰則

安全運転管理者を選任しなかった場合、または選任の届け出を怠った場合、法律に基づき罰則が科せられます。これは、企業の安全運転に対する責任が非常に重いことを示しています。
法改正による厳罰化
安全運転管理者制度は、過去の道路交通法改正によって厳罰化されています。特に、飲酒運転の撲滅や、企業における安全運転管理の徹底を求める社会情勢を背景に、安全運転管理者の選任義務違反や業務怠慢に対する罰則が強化されました。これにより、企業はより一層、安全運転管理体制の構築と維持に真剣に取り組むことが求められるようになりました。
具体的な罰則内容
安全運転管理者を選任しなかった場合、または選任届出を怠った場合の具体的な罰則内容は、50万円以下の罰金が科せられます。これは、道路交通法第119条第1項第13号に規定されています。また、安全運転管理者として選任されていながら、その業務を怠った場合にも、同様の罰則が適用される可能性があります。
さらに、公安委員会からの改善命令に従わない場合など、悪質なケースではより重い行政処分や罰則が科せられることもあります。これらの罰則は、企業の社会的信用を大きく損なうだけでなく、経済的な損失にもつながるため、法令遵守が極めて重要です。
選任以外の届け出が必要なケース
安全運転管理者制度においては、選任時だけでなく、管理者の情報や事業所情報に変更があった場合にも、公安委員会への届出が必要です。
管理者情報の変更・解任時
安全運転管理者の氏名、住所、連絡先などの情報に変更があった場合、または安全運転管理者が退職などで解任された場合には、速やかに公安委員会へ届け出る必要があります。特に解任の場合は、後任の安全運転管理者を選任し、その旨も同時に届け出ることが求められます。これらの変更届出は、安全運転管理体制の正確な情報を公安委員会が把握するために重要です。
事業者情報の変更時
事業所の名称や所在地に変更があった場合、あるいは事業所の閉鎖などにより安全運転管理者の選任義務がなくなった場合にも公安委員会への届け出が必要です。これらの変更は事業所が道路交通法の遵守義務を適切に果たしていることを示すために重要です。
安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務内容は多岐にわたり、道路交通法によって詳細に定められています。従業員の安全運転を確保し、交通事故を未然に防ぐための重要な役割を担います。
道路交通法改正による変更点
道路交通法の改正は、安全運転管理者の業務内容に大きな変更をもたらすことがあります。特に、飲酒運転に関する罰則強化や、最近ではアルコールチェックの義務化に伴い、安全運転管理者はアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認や、その記録の保存といった新たな業務が追加されました。これらの法律改正は、企業の安全運転管理体制をより厳格にすることを目的としています。
法改正の背景
道路交通法の改正は、社会情勢や交通事故の実態を踏まえて行われます。特に、飲酒運転による悲惨な事故が多発したことや、企業における飲酒運転の撲滅が強く求められるようになったことが、アルコールチェック義務化などの法改正の背景にあります。これらの法律改正は、企業の安全運転管理者がより責任を持って飲酒運転防止に取り組むよう促し、社会全体の交通安全意識の向上を目指すものです。
業務量の増加について
道路交通法の改正に伴い、安全運転管理者の業務量は増加傾向にあります。特に、アルコールチェックの義務化により、日々の運行前後のアルコール確認や、その記録・管理といった新たな業務が加わりました。これに加えて、従来の運転者の教育、車両の点検整備状況の確認、運行計画の作成など、多岐にわたる業務を継続して遂行する必要があり、管理者の負担が増大しているのが現状です。
安全運転管理者の具体的な業務内容はこちらから
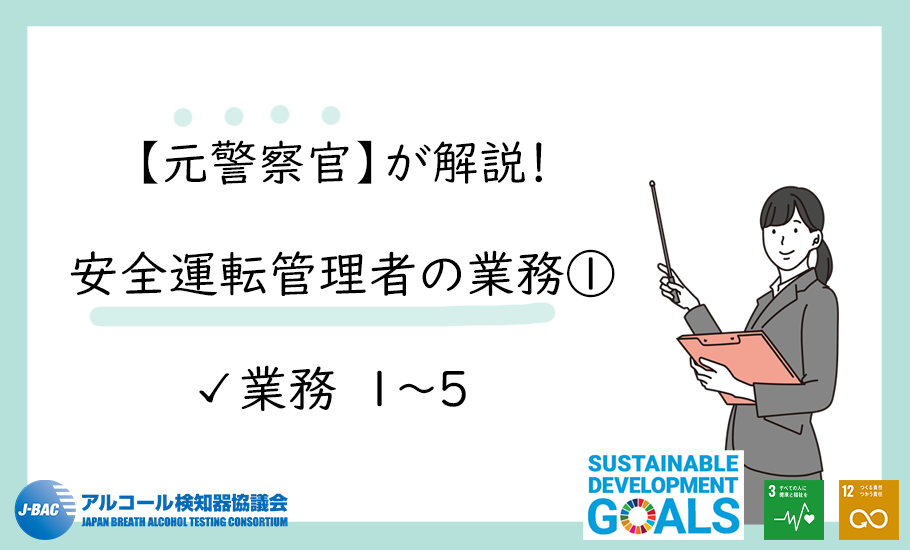
【元警察官】が解説!安全運転管理者の業務①
業務負担軽減に役立つシステム

安全運転管理者の業務負担が増加する中で、その業務を効率化し、負担を軽減するためのシステムが注目されています。特に、車両管理システムは、多岐にわたる業務の効率化に貢献します。
システム導入の利点
アルコールチェック管理システムの導入は、安全運転管理者の業務負担軽減に大きな利点をもたらします。具体的には、手作業で行っていたアルコールチェックの記録や管理を自動化できるため、手間と時間を大幅に削減できます。これにより、交通事故のリスクを低減し、企業の安全運転管理体制の強化に貢献します。
システムを用いたアルコールチェックの運用
システムを活用することで、アルコールチェックの運用を効率的に行うことができます。例えば、アルコール検知器とシステムを連携させることで、測定結果が自動でシステムに記録され、管理者はリアルタイムで確認することが可能になります。また、測定時刻や測定者、結果などの記録が自動で保存されるため、手作業による記録漏れやミスを防ぎ、管理業務を大幅に簡素化できます。これにより、アルコールチェック義務化に伴う業務負担を軽減し、より確実に法令遵守を推進することが可能となります。

2026年最新版!アルコールチェックアプリおすすめ10選|機能比較や選び方も解説




