酒は百薬の長~飲みすぎに注意を~

「酒は百薬の長」ということわざの意味を知っていますか?
この言葉は、古代中国の医書に記された言葉で、適量の酒は体に良い効果をもたらすという意味が込められています。
今回は、この「酒は百薬の長」という言葉について、健康や生活にどのような効果をもたらすのかについて、詳しく解説していきます。
お酒の効果とは?

お酒に含まれるアルコールには血液をサラサラにする効果があります。
血液がサラサラになることで、血流が良くなり、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病を予防することができます。
アルコールには緊張をほぐす効果があり、適量であればリラックス効果を得ることができます。
疲れた心身を癒すために、また社交的な場でのコミュニケーションを促進するためにも、適量の酒は有効な手段となります。
さらに、お酒には食欲を増進させる効果があります。
適量であれば食欲を刺激し、消化を促進する効果が期待できます。
また、脳に働きかけリラックス効果を生み出すことで、食事の楽しみが増えます。
また、お酒は健康効果だけでなく、文化的・社会的な意味も持っています。
お酒を飲むことで、様々な文化的な背景や風習を学ぶことができます。
お酒は社交的な場での人間関係を構築する上でも、重要な要素の1つとなっています。
[ctasem]
適量を守る

飲み過ぎは身体に悪影響を及ぼします。
肝臓や脳に負担を与え、アルコール依存症や脳機能低下、肝臓疾患などの原因になります。
健康を害さない範囲で、適量の飲酒をすることが大切です。
厚生労働省が示す飲酒量の目安は、「1日平均 純アルコールで20g程度」です。
これは日本酒だとおよそ1合、ビールだと中瓶1本になります。
- 女性は男性よりも少ない量が適当である
- 少量の飲酒で顔面紅潮を来す等アルコール代謝能力の低い者では通常の代謝機能を有する人よりも少ない量が適当である
- 65歳以上の高齢者においては、より少量の飲酒が適当である
- アルコール依存症者においては適切な支援のもとに完全断酒が必要である
- 飲酒習慣のない人に対してこの量の飲酒を推奨するものではない
出典:厚生労働省 健康日本21
健康的な飲酒をするためには、適量の飲酒をすることが大切です。
[ctatrial]
まとめ
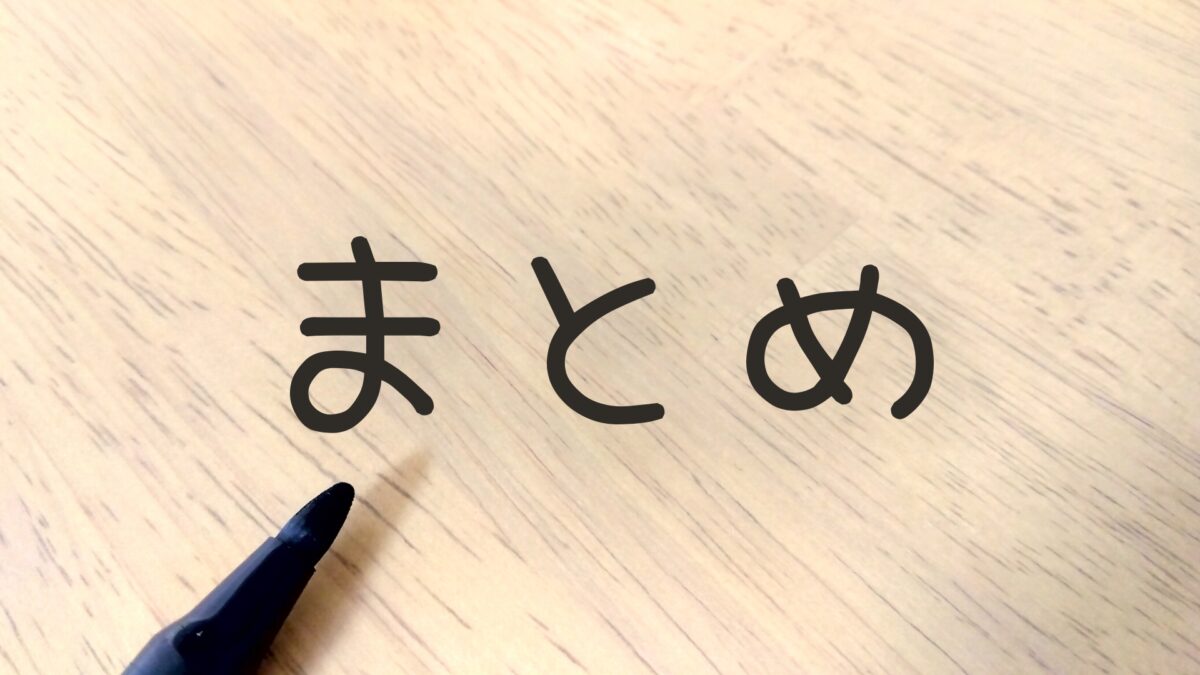
酒は百薬の長ということわざは、まったくの嘘というわけではありませんが、「されど万病の元」という言葉があることも忘れてはいけません。
お酒を健康的に楽しむためには、酒量が過ぎないように気を付けていきましょう。
弊社ではASK認定 飲酒運転防止インストラクターが3名在籍しています。
- 飲酒運転管理にお悩みの方
- 飲酒運転防止の教育にお悩みの方
- アルコールチェッカーの準備をお考えの方
などなど、
気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
[ctainq]
